中二の終わりくらいに人生で初めて学習塾に通い始めると、すぐに駿台模試を受けさせられた。ちょっと緊張しながら会場の高校に行って、試験時間長いなあなどと思った記憶がある。でも数学とか全然わからなくて。やっぱり中一から早稲アカに通ってるやつとかすごいなとか思ったりもしたんだけど、まあ別に俺そんなに熱意とかないしそんなに勉強もしてないしなとあんまり深く考えずに野球ばかりやってその模試のことはすぐに忘れてしまった。
一ヶ月くらい経ってその模試が返却された。で、びっくり。めちゃめちゃ国語の点数が良かった(全国50番とかだった。母数は忘れたけど)。野球の才能が全くないことは痛いほどわかっていたから、安易な俺は勉強の方に舵を切ろうと思った。受験勉強なんて全く考えてもいないのに、毎日勉強ばかりしている奴より俺の方ができるじゃん、みたいな。
まあそれはともかくとして、その時俺は自分のことを国語の天才だと思った。国語の才能に満ち溢れていると思った。文章を書くのが誰よりも得意で、将来はそれで食っていくんだろうなと。坂本勇人にはなれなそうだし、まあ次点でそれもありか、みたいなことをうすらぼんやりと考えた。
で、13年くらいそれを引きずっていたんだけど、社会人になって今俺はそんなに文章を書けないぞと痛感している。そうした絶望を感じてもおかしくないタイミングは幾度もあったんだけど(大学受験の模試で偏差値35とかだったり、まあそんなこと)、なんかここ数ヶ月でその思いを強くしている。うまくいえないんだけど、俺は適切な言葉を適切なタイミングで使うことができない。「東」を伝えるために、「北海道が上の方に位置する地図の右の方」みたいなまわりくどい言い方しかできない。
だから職場でチャットとかをするのが苦手。伝達すべき情報をまとめ上げることにものすごくストレスを感じてしまう。本当はただの一言で伝えられることを、300文字くらいダラダラと論点のわからない文章を書きまくって曖昧な伝達を済ませる、みたいなコミュニケーションになってしまう。そのくせ語尾とか細かい言い回しには気を配ってしまうから、無駄に時間と体力を使う。伝わらなくてもいいから、文章が下手だとは思われたくない。名文家自認が止まらない。
日記って感じでは無くなってしまったので、雑文置き場に投げておく。けど眠いのでここでやめ。続きは明日書くかもしれない。






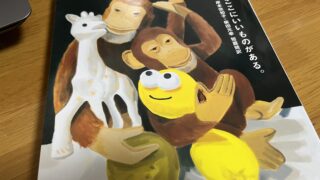
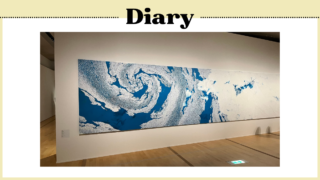
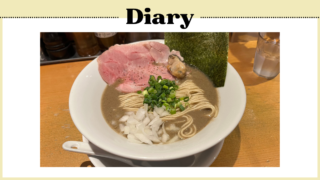
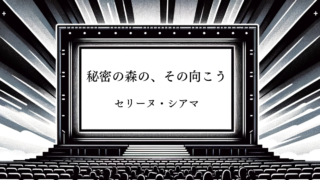



コメント