写真はロシアの街並み。別に画像なんて用意してなかったから、昔Noteに書くときいつも挿入していたこの画像を貼ってみた。理由は特にない。縦長なのがちょっと嫌。
勢いでWordpressを始めてしまった。始めたからには立派なものにしたいと思う。けれどもそうやって力んでしまうせいで、いつも物事を習慣化できずに二歩目くらいで躓いてばかりなのだ。
というわけで、記念すべきサイトの初日記を、ほとんど何も考えずに書いている。構成なんかをし始めたら明日には日記を書いていないに違いないのだから。
今日の振り返り
今日はAmazonでモニターを購入した。これ。
と、Amazonのリンクを貼ろうとした。よくサイトとかで見る広告(?)みたいな感じに。しかしうまくいかない。調べてみると、どうやらAmazonアソシエイツとやらに登録しなければならないらしい。しかもそれなりに審査は厳しいらしい。
というわけで、モニターについては秘密。いや、秘密にする必要はないから商品名だけ書くと、「Dell S2721QS」というモニターを買った。結構高い。あとで機能不足を感じて買い替えるのが嫌だから買ったわけだが、昔からそうした背伸びばかりしている気がする。まあいいや。このサイトをとっとと最強に育ててAmazonアソシエイツに登録し、アホみたいな広告収入を挙げて元を取ってやる、と十二分の大人が夢想したところでこの話は終わり。
で、今日はモニターを選ぶのにだいぶ時間をかけて、気がつけば午前を溶かした。とはいえ三連休初日二日目の溶かし方は尋常でなかったので、まだマシ。そう、今日は三連休の最終日。明日は仕事だし、これを書いている今はもう23時近くで本当に鬱。風呂もまだ入っていない。
午後は友人と柄谷行人の『力と交換様式』を読む。読書会自体はまだ二回目で、少しずつ要領をつかんできたかな、というところ。これについては真面目に他で書く。交換様式Dは、交換様式Aの高次元の回復である。とは。まあ結構説明が繰り返しだったりして読みやすいとはいえないけど、面白い。読書会じゃないと読みきれていなかったと思う(まだ第一章を読み始めたばかりなのだけれど)。
で、飽きてWordpressを調べたりいじって遊んでいたら、もう夜。暗。明日仕事嫌だなあ。
本当はこの三連休で、論文執筆を前に進めなければいけなかったのだけれど。まあ、よしとしよう。頑張ろうね。明日は川上未映子の『夏物語』を読む。ジメジメした夏ですね。
【追記】貼れた。けどなんかおかしいので、ちょっと調べてみます。







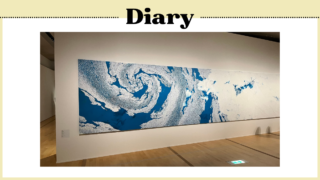

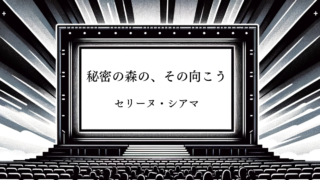

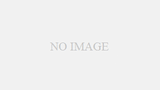

コメント