仕事終わりに東京駅の丸善に寄る。寮で丁寧に読み進めていた違国日記が完結したらしく、今は手元にないから買おうと思う。けれども海外文学の棚をぶらついていると、短編が読みたくなって、アリ・スミスの短編集を手に取る。
短編を読みたい気分になったら、ふとMONKEYの短編特集が欲しくなる。『アホウドリの迷信』が入っている号があったはず。でかい本屋で、まあどの本屋でも売っている本を買うのも微妙だから、雑誌のバックナンバーを買うのがいいかなと思った。多分地元の本屋にも売っているけど。
帰りの電車で、短編を二本読んだ。若い頃出会った赤いスーツケースを持った女を探す話と、アメリカの男子高校生がチアリーダーのコスプレをする話。前者は語りが重層化していて、いかにも短編といった感じ。後者は息子にコスプレを勧める父親のキャラクターが好き。どちらも簡単には要約できないし、したところで面白さが全く伝わらないところが良い。
ところでMONKEYには苦い思い出がある。学生時代、僕は二年間にわたってこの雑誌を購読していた。柴田元幸のファンだったし、あの少し硬い紙質や、軽薄そうで軽薄でないイラストが好きだった。文庫本ばかり買っていた僕には、文章だけでなく紙面全体で作品になるような雑誌という形態に心惹かれた。それに雑誌は所有欲を掻き立てる。No.が振られているだけで、集めなくてはいけないという義務感に駆られる。
ちまちま本屋で過去の号を買い、数年がかりで購読に追いついた。最後の一冊が届いたその一週間後くらいに、ふとその中の一冊を読みたくなり、本棚に手を伸ばす。びっしり詰まったMONKEY。いい眺め。雑誌が揃っていることほど、僕の欲望を満たすことなんてない。
本が抜けない。それほどまでに密に本が詰め込まれているのか。そろそろ新しい棚を追加しなくてはならない。
力を入れて無理やり雑誌を引っこ抜くと、僕が手をかけた一冊だけでなく両隣にあったものまでついてくる。それら三冊は、まるで一冊の本のようにつながっている。
めくるページに、ふわふわとした固形物がくっついている。それが接着剤の役割を果たしている。
カビだった。あまりにも分厚く長くつながったカビだった。あわてて僕はずしりと思い本棚を引きずって、その裏側を見る。
まるでキノコを育てているみたいに、鬱蒼とした菌の巣窟であった。床には小さな水溜まりができていて、壁から落ちた細かいカビが浮かんでいる。そう、僕の下宿は雨漏りをしていたのだ。
そうして僕は、揃ったばかりのMONKEYを、泣く泣く捨てることになる。というか、300冊くらいの本を捨てた。フローリングは痛んでいたけれど、あまり気にすることもなかった。本を捨てることほど辛いことは他にない。何より僕は、ついこの間MONKEYを揃えたばかりだったのだ。
それ以来僕はMONKEYを買わなかった。捨てたやつを買うのは癪だし、新刊を買おうにも忌まわしい過去が頭をよぎってしまう。アメリカ文学に、それ以前ほど興味を持てなくなったというのもあながち間違いではない。
そんな僕が、3年半ぶりにMONKEYを買う。今度はカビを生やさないように気をつけたい。

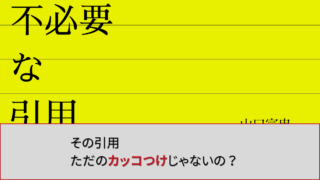
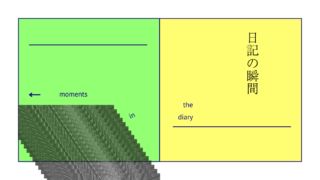

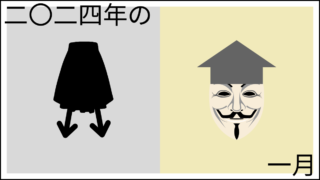





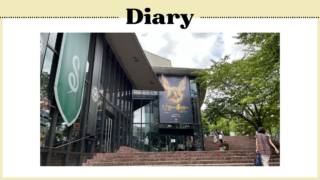


コメント