何の間違いか生徒会の副会長に立候補することになり、選挙演説と称して人のびっしり詰まった体育館の壇上で、所信表明めいた何かをを行うことになった小学五年生の頃のとある秋の日以来、人前で喋ることが苦手という意識を拭うことができずにいる。
正確にいえば、まとまった話をするのがどうもうまくできない。構造化する力、と現在ならばいうだろうその能力は、どうやら社会で綱渡りをする上で極めて重要なスキルの一つらしい。幸か不幸か僕の身の回りには優秀な人間が多く、そういう筋道を立てて話をすることができる人たちがごまんといたのだけれど、その姿を見るとまるで奇術でも使っているかのように僕の目には映る。
その苦手意識から目を背けるために、いつからか僕は「茶化すこと」を覚えた。誰かによって構築された体系に対して、意識的にズレた発言をする。ときにそれは笑いを生むこともあり、僕は自分の言葉がその笑いによって肯定されたかのような錯覚を抱く。
そうした振る舞いによって僕は幸い人間関係を比較的穏便に進めることができていたのだけれど、身についてしまったそうした性質が、もう立派な大人になった僕にとって好ましからぬ影響を及ぼしている。端的にいえば、大人はちゃんとすべきらしい。
まあそんなことは十二分にわかっているのだけれども、ここにはいささか錯綜した僕の葛藤が潜んでいる。本当は僕だってちゃんとしたい。しかしちゃんとできないのだ。
ちゃんとする、というのはつまり、ある種の規範/制度に自分をフィットさせることである。それは敬語を正確に使うことであり、模範解答のような解答をすることであり、話の主要な伏線を回収することだ。生きている上での僕の理想は、まさしくそうした「お手本」の再現である。
しかしそれがどうしてもできない。再び人前で喋ることに話を戻せば、僕の意識がその支配下に収めている時間は、発せられる言葉の前後二秒くらいしかない。もちろんその結果として何を言っているのかわからなくなってしまう。数十秒前に何を話していたのか覚えていない人間が、演説の冒頭で語った内容を回収できるはずもない。
そうした能力の欠如が僕に「茶化すこと」を覚えさせ、ちゃんとしていなさそうな人間としての僕が誕生した。ちゃんとできないから、茶化すしかない。隙間に落ちているユーモアを拾い集めて、何とかやっていくしかない。
ずっとそういう風に自分を分析してきたのだけれど、最近はもしかすると僕は、誰よりもちゃんとしようとしすぎているのではないか、と考えるようになった。一分の隙もない制度以外は制度として認めないような、悪しき完璧主義者が僕の中にいるのではないか。ちゃんとしたいと思うあまり、ちゃんとすることのハードルがおよそ不可能なまで上がってしまい、その非実現性を前にした僕は、ちゃんとしないことでゲームから降りているのではないか。
結構これは僕にとって納得感のある考えだ。僕は新作より古典を好むし、信号はちゃんと守る。法定速度を超えるとドキドキしてしまうし、人と待ち合わせるときは十五分くらい前に到着する。基本的に僕は真面目ちゃんなのである。
ただ、真面目ちゃんなだけでは真面目ちゃんになれない場合もある。論文みたいなかっちりとした文章を書くときであったり、オフィシャルな場で喋ったりプレゼンをしたりするときがその例にあたる。ちゃんとするために、技術が必要とされる場合があるのだ(敬語って難しいですしね)。
ちゃんとする基準が高すぎると、ちょっと技術が要求されるだけで簡単にキャパオーバーを引き起こしてしまう。もちろんそれは能力不足なのだろうけれども、僕の場合は確かにいささか過剰なくらいに形式にこだわってしまう側面がある。ちょっとしたチャットでも助詞の「の」が続くと気持ち悪くなってしまうし、たかだか千字くらいのメモ書きの階層構造を作るために、一時間近く頭を悩ましたりしてしまう。ただの雑談なのにカテゴリーミスがあったら気持ち悪くなってしまうし、本棚の配列が不規則だとすべきことも何も全く手がつかなくなってしまうことがある。
では、僕はどうすべきだろうか。ちゃんとしようと過度に思わないこと。それはそうだ。
多分似たようなことを考えることが巷では流行していて、「ズボラ日記」みたいな漫画が一万くらいリツイートされているのをよく見る気がする。ちゃんとすることに飽き飽きしたのが現代なのだとするならば、僕の悩みはどこにでもあるものなのだろう。
ただし少し異なるのが、ちゃんとしようと思うあまりちゃんとできなくなったという逆説的な事態である。もし僕が本当にそうした状態にあるのならば、その解決策はかなりややこしいものとなる。ちゃんとするために、ちゃんとしすぎないようにすること。ちゃんとする無間地獄。ややこしすぎて、本当はちゃんとしたいのかちゃんとしたくないのかもよくわからなくなってくるが、おそらくこれは真理である。”ちゃんとする”メビウスの輪から逃れる方法は、いったいどこにあるのだろうか。

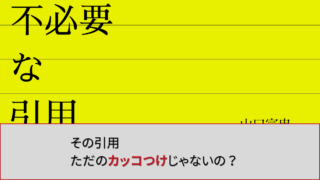
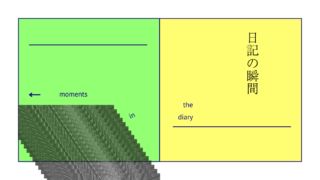

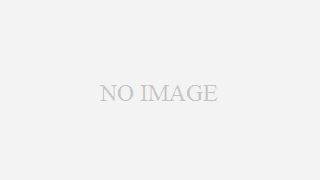
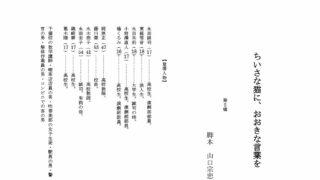



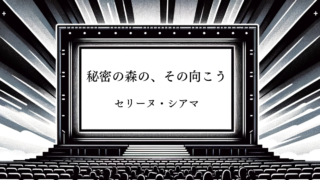



コメント