元旦だが、いつもと変わりのない時間に一人暮らしの部屋で9時ごろ起床。11時に祖母の家を訪れる約束だったが、流しに昨年の食器類が洗われることなく放置してあるので、皿洗いを済ませてから部屋を出ると、結局着く時間は12時くらいになってしまう。
レトルトカレーを食べたあの食器は、確かにその汚れを付着させたまま年を越えたのだと考えると、それも意味ありげな気がしてしまうが、別にそこに大きな意味が隠されているわけもない。ただそう言葉にしてみると、平凡な(それも怠惰な)日常が特別な意味を帯びてくるようで面白い。まあそんなことは屁理屈以前の戯言であり、自分の怠け癖をそうした言葉で覆い隠していくのは流石にもうやめにしようと思う。
電車の中で、年末に買った須藤健太郎さんの『作家主義以後』を読む。「映画批評を再定義する」と副題に示されているこの書物は、各論としてそれぞれ別個の作品に対する批評を取りまとめたものであるのだが、そこに通底しているのは、ある細部(それは往々にして「シーン」という単位に分節化されたものだ)を徹底的に分析することで作品の構造を描き出そうとする著者の意図であるように思われる。
ペドロ・コスタの『ヴィタリナ』の分析で(残念ながら僕はこの作品を見ていない)、映画の終盤に置かれた美しいショットをそれに先立つショットの切り返しとして分析する批評が面白かった。著者の記述はある明確な結論を指し示すべく書かれたものというよりも、切り口だけを設定して一歩一歩地道に進んでいくような印象で、幾度も「もう一度考えてみよう」と議論をぶった切っていくスタイルに、言いようもない爽快さを覚えたものだ。論理的であるということは、いうまでもなくわかりやすいことを意味しない。
まあまだ半分も読めていないので、感想とかを書ける段階にはない。ただ著者の関心が、あるショットが作品の中でどのような意味を持っているのかという問いに貫かれているような気がして嬉しかった。それは僕の関心とかなり近いような感じがあり、その関心に対する理論的な裏付けがどのようなものであるのかを聞いてみたいと思う。
また、この本にはキネマ旬報に書かれていた外国映画レビューのまとめが載っている。僕が自分で見たことのある作品についてのレビューを探していると、その数があまりに少ないことに気が付く。新作を見ないのはよくない。今年はもっと映画館に行こうと思う。
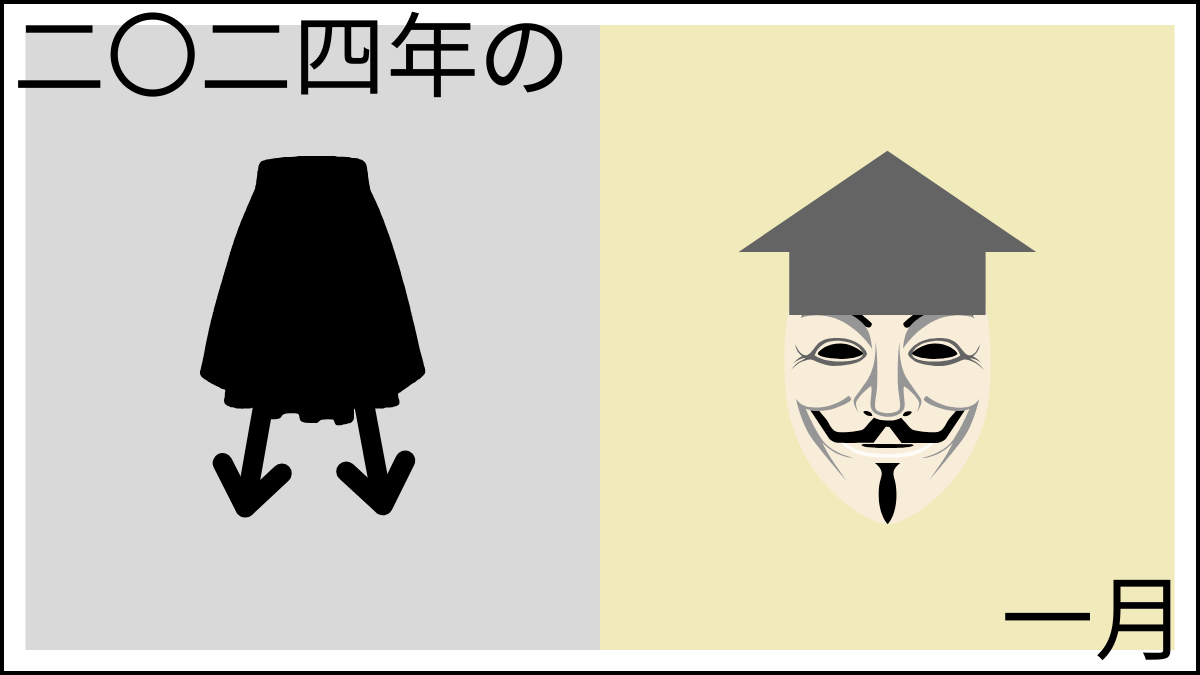





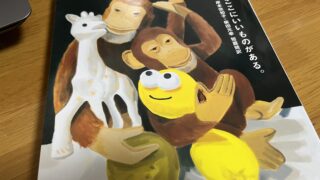
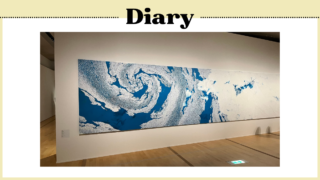
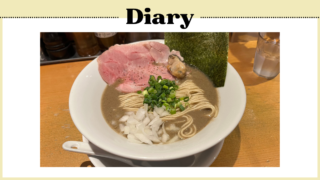
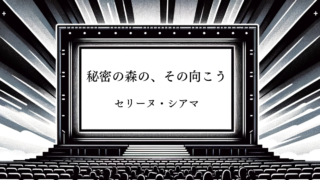


コメント