生活に必要な機能の半分くらいはスマホに頼っていた。
もちろんスマホでなければできないような機能は任せるしかないのだが、そうでない部分——たとえばタイマーとしての機能——みたいなものをかなりの程度スマホで行っていたので、生活の些細な部分でそのリズムが大きく変わってきているのを感じる。
その中の一つに、目覚まし機能がある。といっても、ジャリンジャリン鳴るあの目覚ましのことを指しているわけではない。いや、それもスマホに任せていたのだが、幸い部屋には僕が大学に合格した時、高校野球部の同期がプレゼントしてくれた(その年まで受験生なのは僕だけだった!)かなりうるさい目覚ましがあり、それ自体はいくらでも代替できる。
困っているのは、その音に反応してうっすら目を開けた僕が、真の覚醒に至るまでぼんやりと眺めていた液晶画面が失われたということだ。
まあそれは要するにスマホをいじって布団の中で過ごす時間のことで、スマホ紛失以前の僕はその時間をどうやって削っていくのかを考えていた。ようやく布団から這い出した頃にはもう昼過ぎ、みたいなのは、やはりどう考えても貴重な時間の浪費である。
しかしスマホを持たない今も、その時間の総量は決して減ることはない。むしろ増加している。どうやら強制的に目を開けられた僕が液晶画面の刺激なしに覚醒するにはかなりの時間が必要とされるようだ。
困った。というのも今日も布団の上で目を閉じたり開けたりしているうちに一時間半くらい経ってしまい、結局本当に書きたかった文章を書く時間もなく仕方がなくこんなことを書いているのである。
失われた時を求めて——その失われた時間は全部スマホの中にあると信じていたのだけど、もしかすると別のところにその時間は貯蔵されているのではないか——
そう考えると、どこかへ消え去ってしまった時間をめぐる旅はまだまだ続きそうだ。
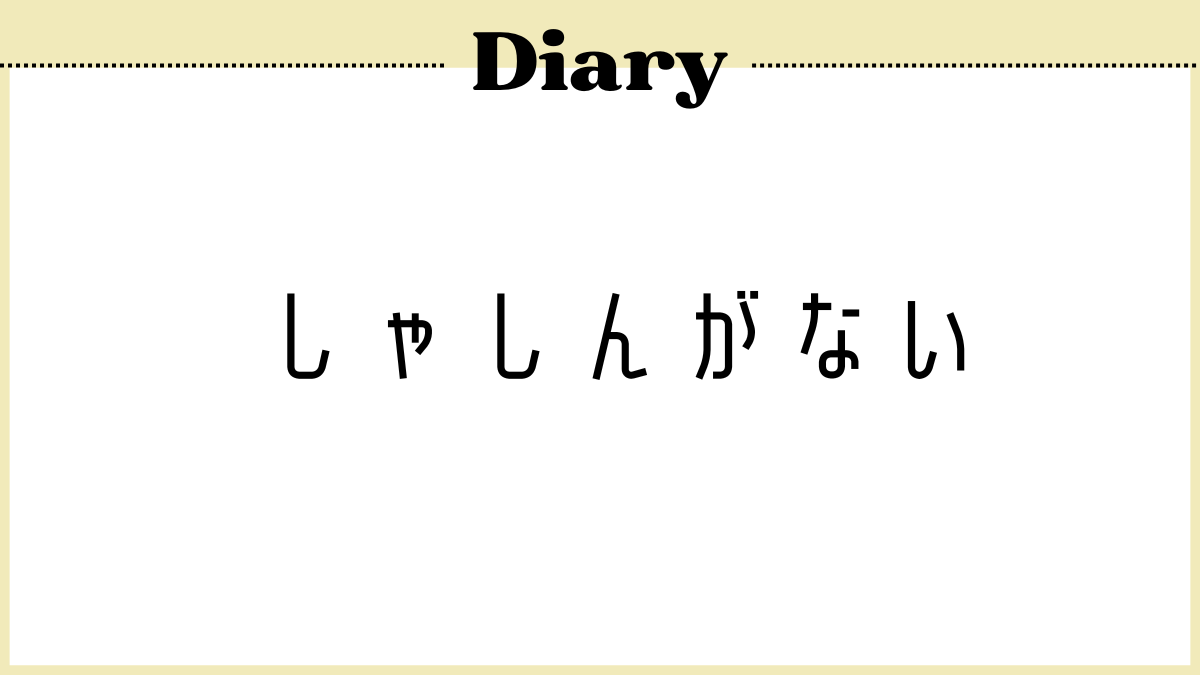
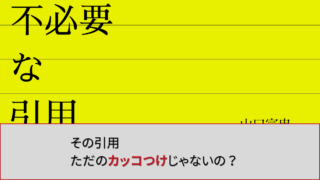
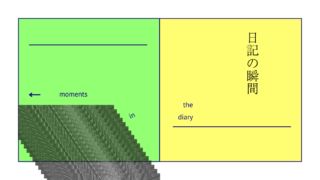

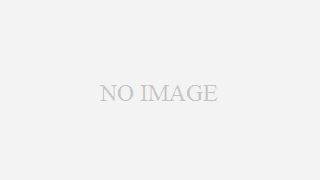
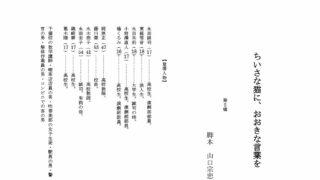



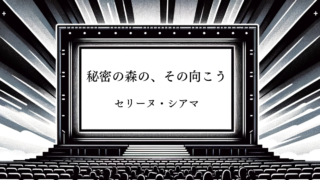



コメント