仕事から帰るとすぐにたまった洗濯物をまとめ、近くのコインランドリーに向かう。洗い終わるまでの一時間で、賞味期限の近いタコを調理する。
ニンニクと唐辛子をオリーブオイルで炒め、玉ねぎを入れてさっと加熱。そこにぶつ切りにしたタコを入れて、トマト缶を流し込む。なぜか家にあるオリーブなんかも放り込んで、30分ほど弱火でコトコト煮ていく。
洗濯物と煮込み料理が作り出した二重の空白を、何で埋めるべきかと考える。しかしこの答えはほとんど自明だ。とっととシャワーを浴びてしまおう。そうして一日のノルマを綺麗さっぱり終えてしまうのだ。
自分でも驚くくらい無駄な時間がない。分刻みのスケジュールで行動するキャラクターがいたよな、と小学生の頃に読んだブラック・ジャックの記憶を引っ張り出し、そこで出てくる成金実業家と自分を重ね合わせる。僕はやはりできるやつだな、とほくそ笑みながら、狭い風呂場で髪を洗う。
バスタオルがない。
髪を泡立てている手が止まる。バスタオルがない。ただの一枚も、身体を拭くためのタオルが存在しない。
数百メートル先の無駄に綺麗なコインランドリーの中で、今頃そいつは暖かい風を浴びてぬくぬくと乾いている。しかしお前がカラッと乾燥させてもらえるのは、僕を拭くというお仕事があるからだ。その仕事を放棄して、お前だけがフワフワになってどうする。そのフワフワは、僕を拭くための柔らかさでしかないのだ。
などと憤るが、濡れタオルを何度も絞りながら身体を拭き、ハンカチみたいな小さな布切れで凍えながら水気を取るだけしかできない。いつもより二倍くらい時間をかけて、ドライヤーで髪を乾かす。
何だか一日中が忙しなかったので疲れてしまい、映画を見ている途中で23時くらいに眠り込む。結局タコは硬いまま。
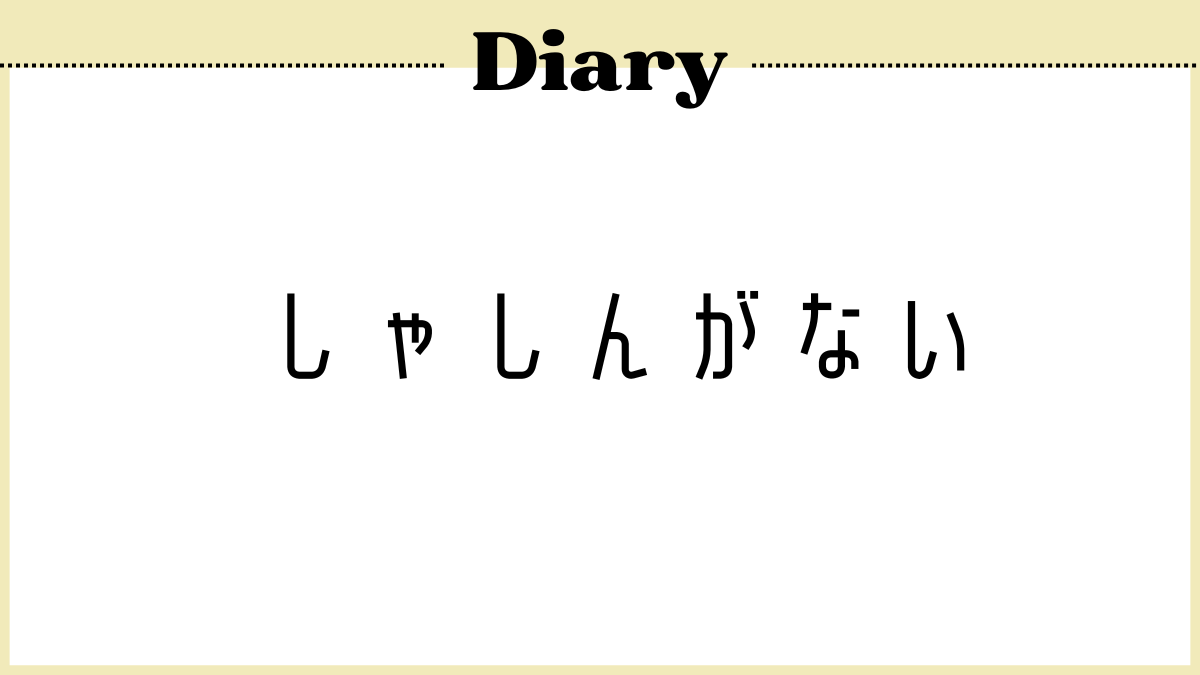
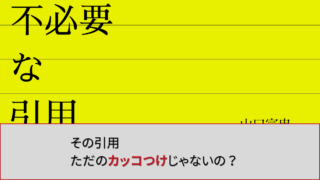
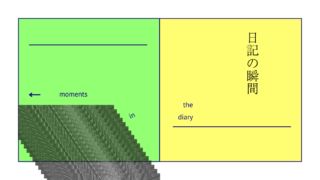


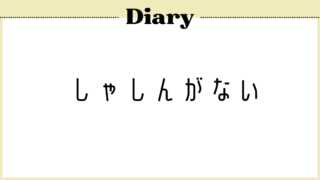
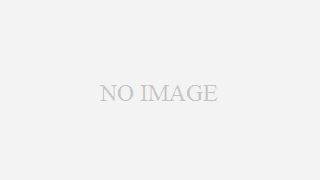

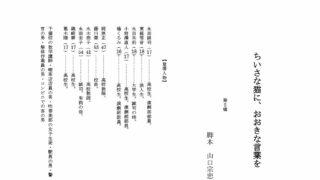
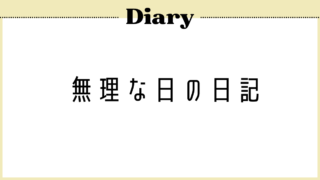


コメント