ジャームッシュは常に正しい。
映画言説の中でこうした考えは当たり前のものとして定着しているのかもしれないが、なにぶん不勉強なので、ジャームッシュがどのように語られてきたのかはほとんど知らない。しかし極めて個人的な感覚として、ジャームッシュの映画を見る時に常に感じるのは、その律儀なまでの「正しさ」である。
プチ批評
『ダウン・バイ・ロー』の驚き
そのことに思い至ったのは、二年ほど前に『ダウン・バイ・ロー』を見た時のことである。協力して脱走した三人の囚人。些細な原因から彼らはわずかな時間別行動をとることになる。
夜の森の少しひらけた場所で火をくべている三人。一人は元の場から左手奥へ、もう一人は右手奥へと消えていく。残された一人はその場にとどまり、座り込んで肉を貪っている。
続くシークェンスで、別れた三人がそれぞれ単独のショットで捉えられるのだが、そこで何よりも素晴らしいのは、画面の左奥に消えた人間は画面左方へ歩くものとして、右奥に消えた人間は右方へ歩くものとして、きちんと整理された上で構成されている点にある。
それまでの僕はおそらくサブカル的にジャームッシュを消費していた。面白いのか面白くないのかよくわからないが、これを面白いと言わないと自らのセンスが否定される。それはほとんど踏み絵のようなものであったのだが、正直なところ僕が彼の映画で好きだったのは、『ナイト・オン・ザ・プラネット』の第一話に出てくるウィノナ・ライダー演じるタクシードライバーに限られていた。煙草をばかばか吸う、ポスターに出てくるあの有名な女の子だ。個人的に、説話に回収されないあのダラダラと続く会話や、唐突に繰り広げられる「演技」としての虚構性を、ジャームッシュ固有の美点として捉えることは一切できなかった。
そんな風に、熱狂とは程遠いところでジャームッシュを見ていたから、『ダウン・バイ・ロー』で初めて気がついたそのど真面目な図式性に、僕は結構驚いてしまった。オフ・ビートな作風、みたいな形容は、この正確さを語った後に補足として付け加えられる程度でなければならない。
その気づきは確かな感動であった。その後はどのジャームッシュの映画を見ても、一つ一つの編集が映画空間を正しく構築していることに目がいってしまう。こんなに「正しい」映画は滅多にない。
ジャームッシュの「西部劇」
そのジャームッシュが、西部劇を撮る。
西部劇とは、言うまでもなく空間の構成が作品の質に直結するジャンルである。馬たちの追いかけっこは、曖昧な位置関係では決してサスペンスを構築しえない。別個のショットで捉えられた二者が、それでいて「追うもの」と「追われるもの」としての連携を形作らなければならないからだ。
本作も西部劇の伝統にならって、「追うもの」と「追われるもの」の関係が物語を前進させている。疾走する馬たちのチェイスこそ描かれていないが、確かにこれは「真面目な」西部劇である。
もちろん本作でもジャームッシュらしく「正しく」空間が構成され、観客は登場人物の位置関係を正確に把握することができる。
しかし、ジャームッシュがこれを撮る必要があったのかは何とも言えない。彼の美点は、乾いた都市の中で生きる若者たちを軽やかに描きながら、正当な映画史的伝統を引き継いだ「正しい」画面を構成する、その混淆の中にあるような気がするからだ。






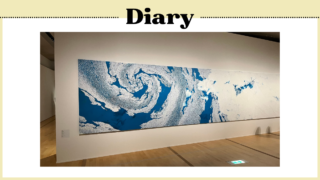
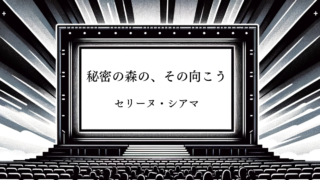

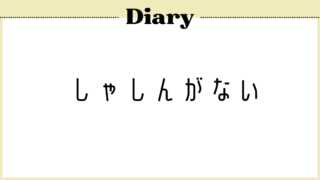


コメント