新しく出た美学の入門書を数日前に読み終えた。
著者はバウムガルテンに関する著作で博士論文を書いた、井奥陽子さん。市民講座の講義をもとにした新書とあって、語り口も柔らかでとても読みやすい。
本書を通して一貫しているのが、美学にまつわる様々な概念が成立する過程を、「AからBへの移行」として捉えている点だ。一つ例を挙げれば、芸術家という概念は「職人から天才」へとその力点が転換したものとされる。芸術家=天才という定式が当たり前になっている現代という時代は、この思想史的な流れを意識することで相対化される。
この本を含め、美学にまつわる入門書を三冊くらい読んでみようと思っている。そのまとめも一つの記事にして公開したい。
しかしこの本にバウムガルテンの名が全く出てこないのにはびっくりした。ど専門を外した、ストイックな著述。なかなか興味深いですね。

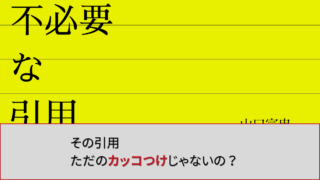
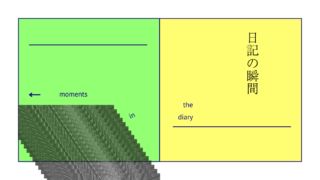
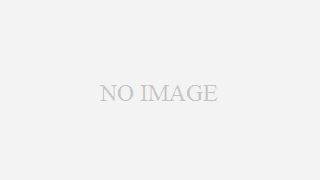


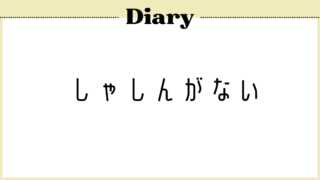
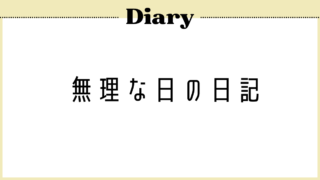




コメント