仕事終わりはやっぱり疲れていて、朝とは異なり座って帰路につくのだけれど、なかなか本を読んだりする気力が湧かずにスマホばかりいじってしまう。
これはあまり良くないぞ、ということで、今日の帰りは漫画を読もうと思う。しかし手元にはなく、東京駅の丸善に寄って漫画を買う。
数字であそぼの七巻を手に取る。すると購買意欲がむくむくと沸き立ってきて、これ描いて死ねとドリフターズの新刊も抱え込んでしまう。三冊も漫画を買って、その中に新しい作品がないのも保守的だよな、と自分勝手な言い訳をこしらえて、アンダーカレントという漫画にも手を出す。僕は漫画に疎いから、今度実写化されるという情報しか持っていない。面白いといいな。
今週末は京都。くるりの京都音楽博覧会を見にいく、というのが一応の口実。会いたい友達はたくさんいるのだけれど、わずか三日の間に誰に会うべきか、みたいなことを考えたくなくて、あんまり人を誘うことができない。
それに京都から帰ってくる時のことを考えると、この時点で少し憂鬱になってしまう。なんてややこしい人間なんだろうね、僕は。
とはいえ、もちろん楽しみ。かなり楽しみ。あと村屋に行きたい。やはり東京に村屋は存在しない。
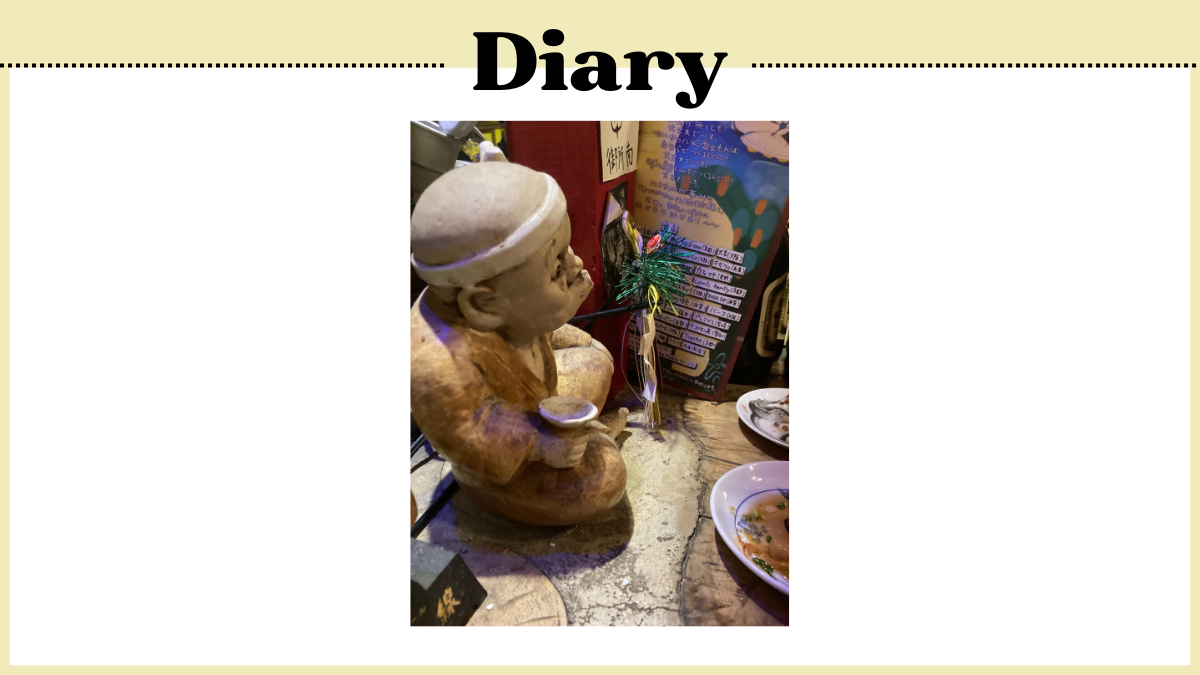






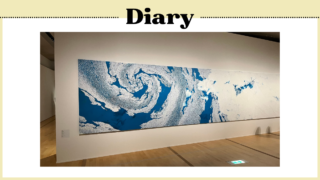

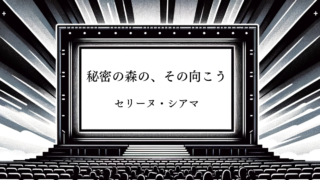



コメント