午前中に『砂の器』を見て、午後からは川崎にビクトル・エリセの『瞳をとじて』を見にいく。
映画の開演までに時間があったので、ブックオフを冷やかしに行くと、ワシーリー・グロスマンの『人生と運命』の第一巻が四冊くらい売っている。在庫が余っているのか、元の値段の半額くらいまで値引きされていて、ちょっと不思議な気持ちになる。この在庫の多さはほとんど村上春樹みたいだ。それにこの分厚い小説はスタッフオススメの自己啓発本、みたいなエリアに並んでおり「効率よく頭を使うってこういうことなんだ!」みたいなPOPがついている。このずれ方は面白いと思って写真を撮ろうとするが、無闇に本屋の棚を撮るのはあまり好ましくないと思い直してやめる。
ブックオフの入っている商業施設のエスカレーターで、偶然中学生くらいの男子二人と目が合う。急にニヤニヤとし始めた彼らが、どんな悪口を僕に言っているのか想像してみたりするが(「髪ボサボサ」、「丸めがね似合ってない」等々)、この野球部的な街で出会う中学生はあまりよい記憶を喚起しないので忘れることにしたい。が、多分できない。
エリセの新作。冒頭の劇中劇がかなり長い会話で、その時点でかなりうとうとしてしまい、少し不安になる。それだけでなくこの映画ではどの会話も省略されることなくグダグダと続くのだが、しかし物語の中盤でそれこそが一つの主題系をなしていることがわかると急に面白くなってくる。
編集される会話/編集されない会話。切り取られる会話/切り取られない会話。前者が映画で後者が人生だと言ったら退屈な二分法にすぎないが、そのバランスをとろうと格闘することこそがビクトル・エリセの映画/人生なのだろうと思うと、かなり泣けてくるものがある。
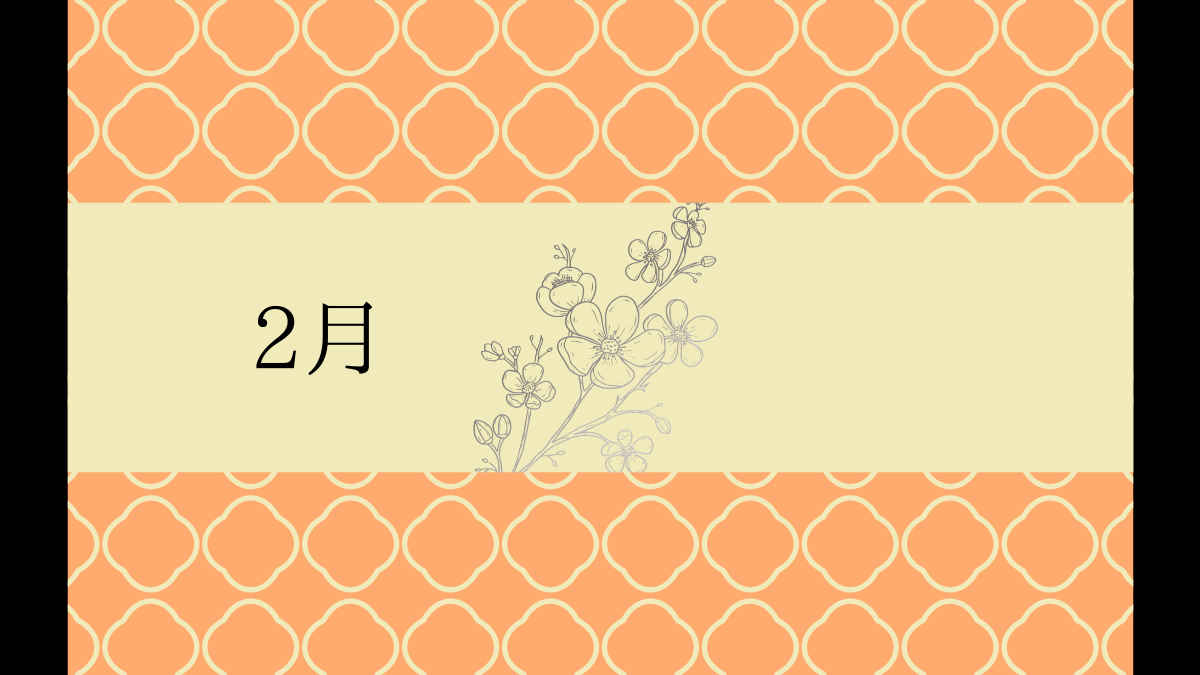





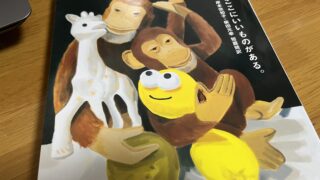
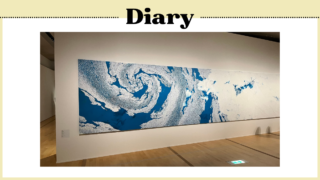
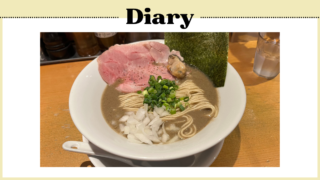
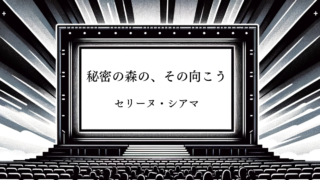


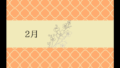
コメント