職場の人とジンギスカン屋に行く。
そこではこんもりとした山型の鉄鍋に羊肉ともやしが載っているタイプのジンギスカンではなく、鉄網で羊肉を焼いていくスタイルの料理が提供されている。まあそれは焼肉というほかない料理で、ちょっと癖のある脂の旨みが香ばしく口内を満たしていくのが楽しい。
結構ガヤガヤとした居酒屋の雰囲気で、複数人で行くことを想定された店のつくり。その店内で端の方の席にひとりで座る三十歳くらいの女性がいる。油はね防止の紙エプロンを真っ直ぐに身につけ、一枚一枚丁寧に肉を焼いていく姿は凛としていて美しい。背筋を伸ばしてベストな状態に焼き上がった羊肉を玩味する彼女の耳には、だんだんと声の大きくなっていく僕たちや他の客の会話が聞こえているのだろうと思うと、僕はふとした瞬間に恥ずかしさというか情けなさを感じてしまう。
ひとりの人間の正しさに、集団は何をしても勝てやしない。でもお酒が入っていくにつれてそんな認識はどんどん薄れてしまい、結局僕は職場の人というグループの中で、集団であるがゆえの正しさみたいなものを身に纏っていき、ある種の傲慢さでもって振る舞うようになってしまう。
気がつけば彼女の姿はもうない。おそらくはエプロンを畳んで店を出たのだろう。そんなことを勝手に想像しながら、彼女に張り合うため僕も退店時にエプロンを綺麗に四つ折りにしてやろうと決意をしたのだが、その薄い紙の記憶はいつからか綺麗さっぱりなくなってしまっている。
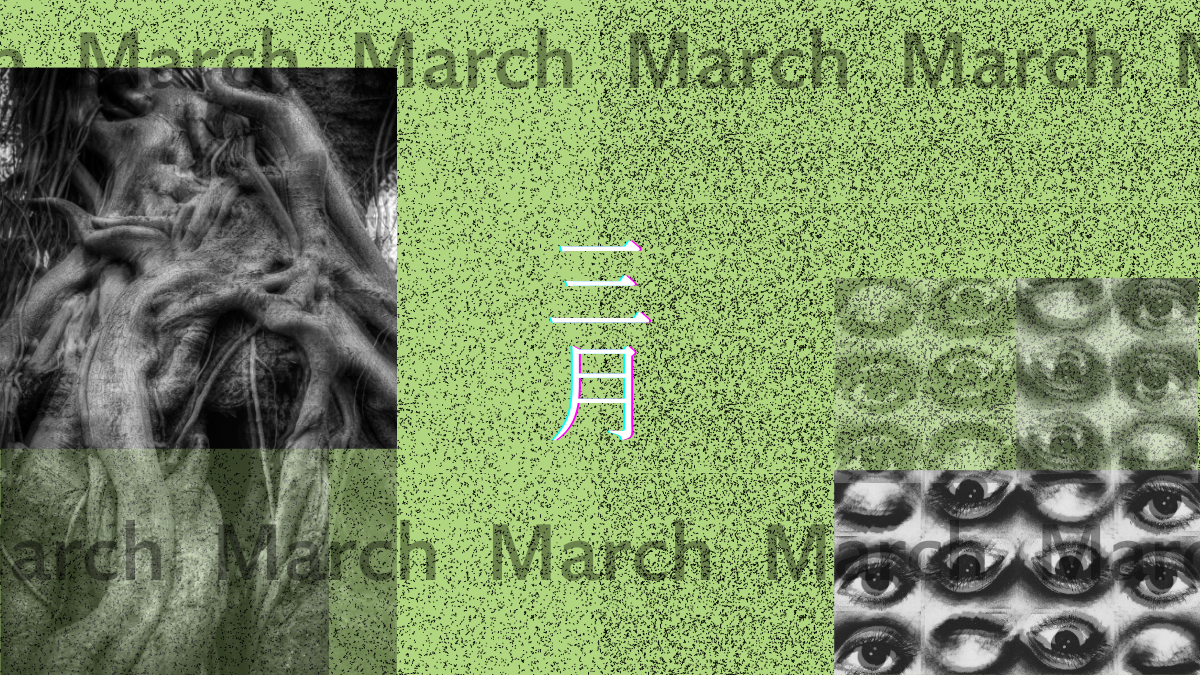
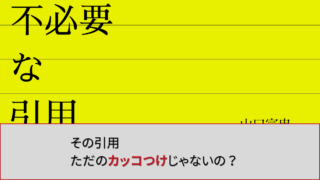
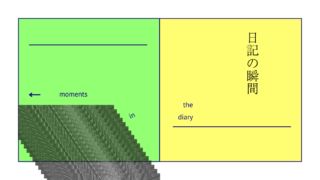

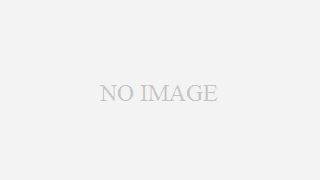
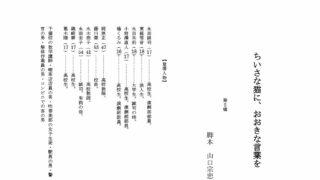



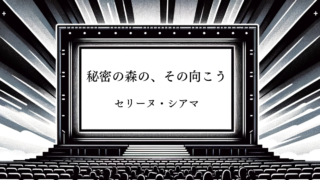


コメント