どこかで遅延が発生したのか、帰りの電車がいつもにまして混みあっている。人が押し合いへし合いしている狭い密室で、観光客と思しき人たちが仲間たちとニヤリと笑いつつ、時折本気で嫌がっている表情も浮かべたりする。まあそりゃそうだと思う。満員電車って海外では結構知られているのかしら。
うっかり最寄り駅で開くドアから最も遠い位置に陣取ってしまったので、固まった人の群れをかき分けて降りるのが難しい。電車が駅に到着し扉が開くと、すみませんと小さく声を出してみたり、わずかにできた人の隙間に肩を差し込んでスペースを作ってみたり、色々の工夫を凝らして少しずつ外に近づいていく。
しかしどうにもうまく進まない。大きな荷物が多いというのもあるだろうし、乗客の多くが満員電車に慣れていないという理由もあるだろう。いつもはここまで混雑する路線でもない。
とはいえここで妥協して最寄り駅で降りることができなかったら、ただでさえいつもより少し長く仕事をしてしまってムカムカしているこの気持ちが、さらに腹立ちにまみれてどす黒く変色してしまうことだろう。映画も見たいし、読みかけになっている本の続きも読みたい。帰路に着く僕がとにかく確保すべきは労働から離れた時間であって、それを守るためには多少とも己を鬼にして前進を続けなければならない。
そんなことを考えていたとき、僕はいつもの僕が厳しく嫌悪するあの不機嫌な労働者の顔をしていたのだろう。勝手に自己を正当化し、開いた扉に向かって前に進むだけの機械人形と化した僕は、ぐいと身体を押し込んだその場所に立っている女性が浮かべた不愉快そうな表情に気が付きつつも、それを決して目に留めようともせずひたすらに降り口を目指す。
他人を蹴散らして降り立った最寄り駅はやけに涼しかった。その女性の顔がふと思い出される。申し訳ないことをした。もしかすると彼女は観光客で、この旅行を楽しみにしてきたのかもしれない。その喜びに僕が水をさしてしまったのならば、これほどまでに醜悪な行為もないだろう。
こうした繰り返しで人は心に闇を宿すようになり、他者に対して無関心となっていくのかもしれない。そう思うと、邪悪さへと向かう扉があの満員電車の扉であったかのような気がしてしまう。
反省。






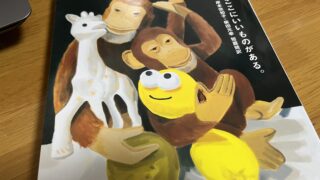
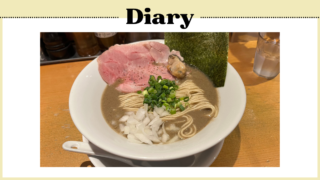

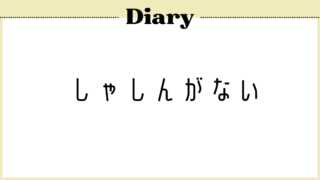

コメント