同僚から洗濯機を貰い受けることになったので、引っ越してから三ヶ月あまり、あとはガスコンロを購入すればこれで一通りの家具が揃ったことになる。
そういうわけで、昨日も何度目かのコインランドリーに行ったのだが、おそらくはこれが最後になる。無人の店とはいえ、どこか寂しさを感じないわけでもない。誰もいない店内で、一人衣服を放り込みながら、そんなことを考える。
いつも通り1000円の洗濯コースを選んでボタンを押すと、先にお金を入れてくださいと言われる。結局最後まで同じことを言われ続けてしまった。唯一財布に残された千円札を両替機に突っ込んで百円玉を拵え、それらを片手で掴みながら硬貨の投入口に一つずつ入れていく。十枚の百円玉を握りしめ、それらを落とすまいと掌に神経を張り巡らせるようなことは、もしかするとこの先一度もないかもしれない。
一時間が経ち、再びコインランドリーにやってくると、そこには今までみたこともないほど多くの人(といっても七、八人程度)がいる。洗濯が終わるのを待っているのか、それとも洗濯機が空くのを待っているのか。しかしそんなことはわかるはずもない。僕に内緒で引退セレモニーが企画されていたのだ。そんな妄想をしながら衣服を袋に入れていくと、薄いビニール袋が破れてしまう。僕はパンツや靴下を落とすまいと、良い匂いのするかつての汚れ物を抱え込み、一人トボトボと夜道を帰る。

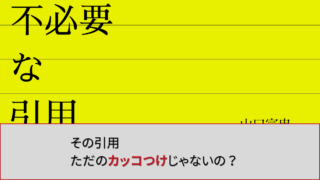
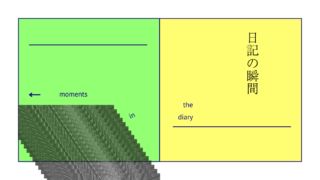

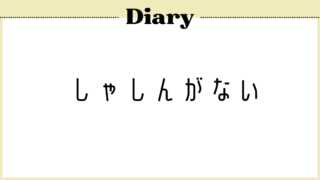
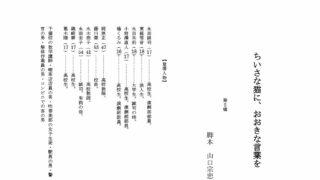
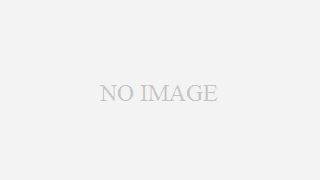





コメント