新しい本棚が届いたので、場所がなく二ヶ月ばかり段ボールの中で放置されていた結構な数の本と久しぶりに対面する。
段ボールは三つ。一つはワンピースと村上春樹が入った箱。もう一つには芥川龍之介から綿矢りさまで(これは時代順でもあり名前順でもある!)が入っている。最後の一つには雑誌や新書、経済学史の本からみうらじゅんのエッセイまで、大小様々の本が雑多に詰め込まれている。
本棚に入らないから箱の中で眠らせていたというのは本当だ。とはいえ大体の段ボール箱は開封して無理やり棚に押し込んだのだから、結局その選択には僕自身の価値判断が含まれていることになる。
正直なところ、ここにはこれから先もう読む機会がないだろうと薄々感じている本たちが多く含まれている。ならばなぜ持ってきたのか。別に実家に置いてくることもできたはずだ。
センター試験の帰り道に購入した『ドグラ・マグラ』や、Macを買ったときについてきたAppleのシールを表紙に貼り付けた『資本論』の第一巻。『ルネサンスと宗教改革』というカバーのない古い岩波の一冊。ほとんどは古本屋を冷やかしている時に気まぐれで買った本たちで、購入時に「読むぞ」と思ったまま興味を失ってしまったものもあれば、買う時点で「これは一生読まないな」と感じ取っていた本もある。

まだ読んでもおらずこれから読むこともない本を新しい本棚に整列させていくと、購入時の記憶がじわじわと思い出されてくる。居酒屋でのバイトが早く終わり、寒空の下自転車を全力で漕いで向かった閉店間際のコミックショック。真っ白な蛍光灯が不健康に照らすお世辞にも広いとはいえないその店は、僕が二回生くらいの時になくなってしまった。
下宿先から近く、確か十一時までやっていたその店に僕はほとんど毎日のように通っていた。何せこの店、しょっちゅう値付けを間違えるのだ。ブックオフでは定価の七割くらいの値段にしかならない講談社学術文庫やちくま学芸文庫が、この店では時折百円で売り出されたりもする。そうして僕はどうせ読みもしない社会学の古典であったり、谷崎訳の源氏物語であったり、バウムガルテンの『美学』であったりを、これはお得だとばかりにごっそりと購入して既にぎっしり詰まった部屋の本棚に積んでいく。
しかしいつからか閉店時刻が七時になり、どんなに急いでもバイト終わりに立ち寄ることもできなくなると、食欲を失った老人が一気に痩せ細っていくかのように、店内からは本がどんどんとなくなっていき、とうとう「来月閉店します」との紙が店先に張り出されたのだった。
最終営業日の二日ほど前に、僕はコミックショックを最後に訪れた。在庫処分のため、ただでさえ値付けの甘いこの店の本たちは全品五割引とかいう破格の値引きをされていた。閉店する悲しみ半分、割引の楽しみ半分で、僕は小一時間ばかり店内を物色した。
しかし目に留まる本が一冊もない。チェーン店とはいえ元々品揃えの良い古本屋ではなかったし(小さい店だったから仕方がない)、個人店のような選び抜かれた本が並んでいたわけでもない(チェーン店だから仕方がない)。それでも地の利を活かしてというべきか、訪れると必ず一冊は「これは」と思わされる本が目立たずにひっそりと陳列されていたのに、その日の棚は質量ともにスカスカであった。
僕は何の本も買わずに店を出た。それが最後になった。
コミックショックの跡地は学生が運営するジムになり、それもすぐになくなって整体院になった。順番の記憶が曖昧で、間違っている気もする。もしかすると居酒屋になった時期もあったかもしれない。
本棚を整理していて、そんなことを思い出した。読まない本を持ってきてよかったと思う。
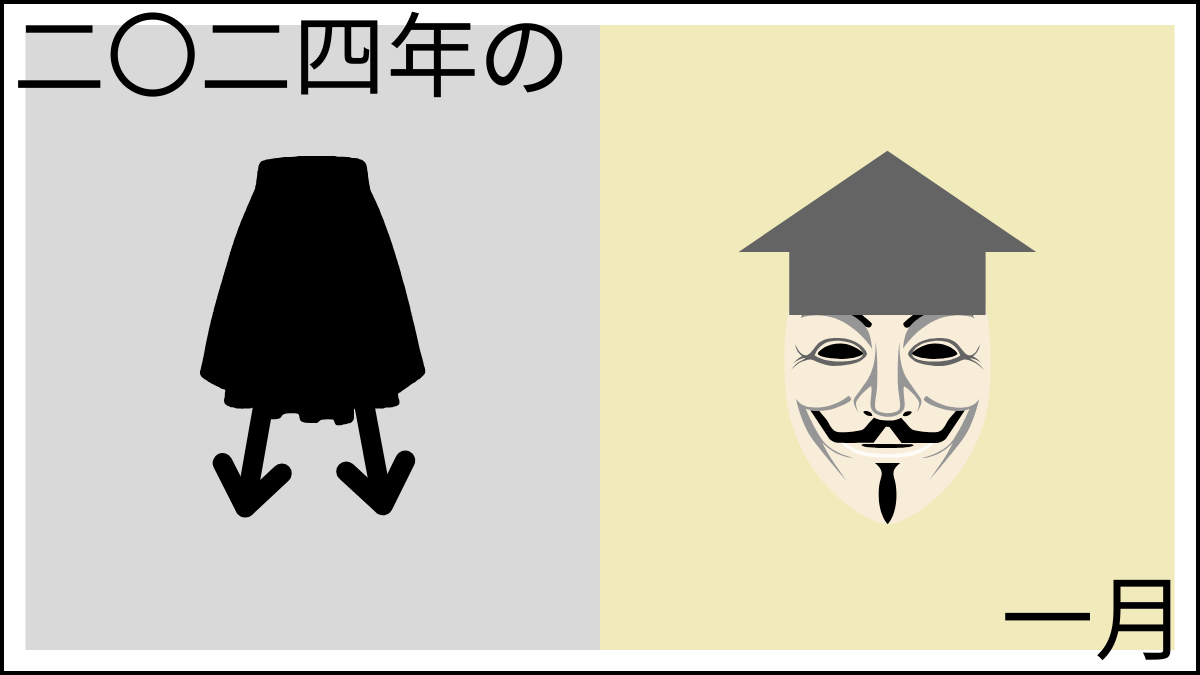
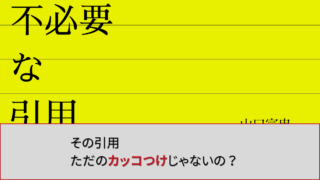
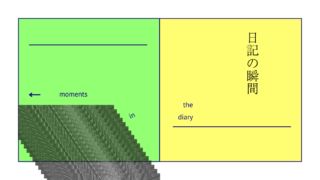

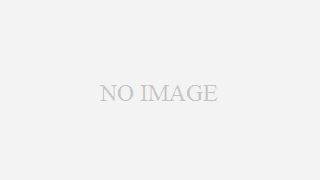
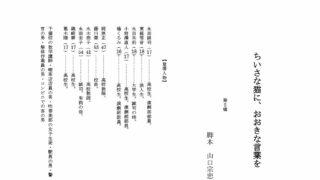



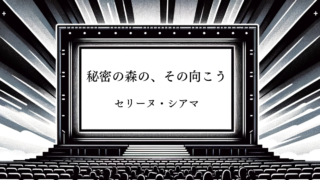


コメント