最近少しタイピングが早くなってきた。ブラインドタッチのほんの手前くらい。
とはいっても、完全に自己流で、ホームポジションなど意識したこともない。そのせいなのかはわからないが、日本語入力の「、」と「。」と「・」をよく押し間違えてしまうし、oとpの位置も曖昧にしか把握していない。
しかしキーボードをほとんど見ずにタイピングができるのが、こんなにも気持ちの良いことだとは思いもしなかった。その気持ちよさが、文章を書く運動をドライブさせてくれるような感覚もある。
ここらで一回、自己流から離れてある種の規範に身を置くべきか。型破りになるためには、型を知らなければならない。擦られすぎて陳腐と化したその文句に素直に従うのも悪くはないのかもしれない。
ところで、向井秀徳という男がいる。ナンバーガールとZAZEN BOYSのフロントマンで、福岡市博多区からやってきたおもしろおじさん。焼酎とメガネの似合う、ジャキジャキとしたギターを鳴らすバンドマンだ。
大学に入った頃くらいから、僕は彼のことがものすごく好きになり、その振る舞いを模倣しようとしていた。会話というものをコミュニケーションではなく、離散的な言葉の積み重ねとして定義しているような感じのあれ。僕が他人の話をほとんど聞かずに、自分の言いたいことばかり言ってしまうのも、かつて向井秀徳のような言い回しを練習していた名残なのかもしれない。
そんな彼は、自らの奏法を「オレ押さえ」と呼ぶ。僕はギターに明るくないので詳細はよくわからないが、その言葉の響きからして自己流の弾き方であるのだと思われる。
ちょっとその概念を拝借してみようと思う。自分勝手なタイピング。オレタイピング。あまりにもダサいが、そのダサさを一度引き受けなければ、人は向井秀徳のようになることはできない。
と適当な一般論をこねくり出したが、向井秀徳がダサさをその極限においてかっこよさに反転させることのできる人間であることは言うまでもない。大抵の人間は、非洗練をある種の鋭さに書き換える能力を持ちえない。それはもちろん僕にも当てはまる。
まあ、本当に適当なことばかり書いたが、何かを身につけないための言い訳として向井秀徳を持ち出すのは間違っているし、自分が彼のように無軌道な雰囲気を出すことも難しいだろうから、僕は大人しくホームポジションに指を置くことにしよう。
しかし一人暮らしを始めたら、とりあえず二階堂の一升瓶でも買って部屋の片隅にどんと置こう——どうせ酒浸りになんてなりやしないし、誰に文句を言われることもないのだから。

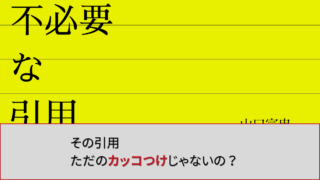
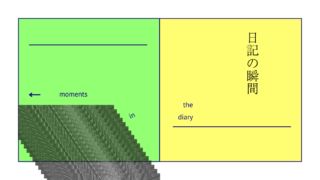

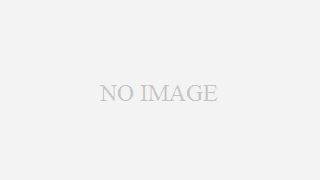
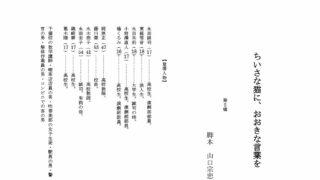

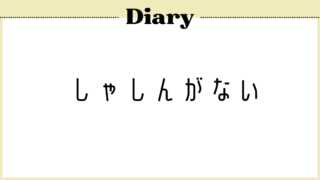
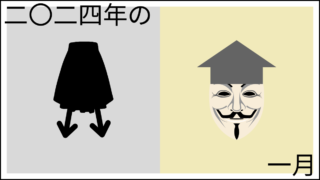



コメント