ワードプレスをいじるのが楽しくて、論文執筆が捗らない。本当に捗らない。本当に締め切りが近いのに。締め切りが近いことを言い訳にして、いろんなことを先延ばしにしているのに。
自分一人で運用しているのに、他人に記事を書いてもらいたくてうずうずしている。執筆するまでの流れとかを考えたりしている。しかしそのためには僕がこの場所で何をしたいのか、それを明確にしなければならない。その前におもしろ文章を書きたい。こんなどうでもいい日記ではなく。
あと記事用のアイキャッチを作りたい。ジャンル別に下地を用意して、ちょっと改変を加えるみたいに。でもちょっとめんどくさい。
ただこんな風に作業の流れとかを考えるようになったのは、やはり僕が社会人になったという証左だと思う。昔は何も考えていなかった。あまり今も考える方ではないが、それでも。
ただ、果たしてこれが良いことなのかはわからない。中身を考えるのではなく、機構とかシステムのようなものばかり考えるのは、僕がなりたかった自分ではない。もっと楽しいものは楽しいままに受け入れるのがなりたい自分ではないか。こんなのノートを綺麗に取って満足する大して賢くもない少年少女ではないか。ぐちゃぐちゃのノートの中に、綺羅星のごとく輝く才能。そんな風に生きていきたい。
まあ、今はそれが楽しいのならそれでいいやとも思う。どしどし運用とか考えてしまえ。一人だが。
偉く抽象的。それは今日が代わり映えのない平凡な1日だったからなのだろう。







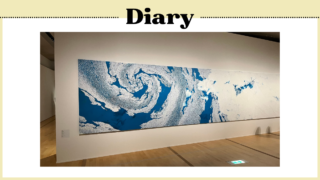

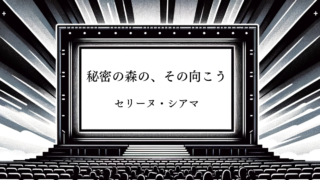

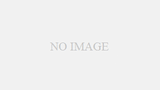

コメント