『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』を読んだ。結構長い間自分が考えてきたことが整理されたような気がしてよかった。たとえば次のまとめ。
① 読書——ノイズ込みの知を得る
② 情報——ノイズ抜きの知を得る
ここでいう「ノイズ」とは、ある個人にとってコントロールのできない問題のこと。大雑把にまとめてしまうとそれは「社会」のことだ。
社会は変えられないのだから、変えられるところから変えていこう——そうした諦めが可視化されたものとして、著者は「片付け本」を取り上げる。
〈部屋〉=私的空間を「聖化」することが、自分の〈人生〉が好転することに直結する、というロジックが「片付け本」の趣旨である。しかしそこには、本来〈部屋〉と〈人生〉の間にあるべき〈社会〉が捨て置かれている。
部屋という聖域を作ること。自分の形を変えることによって、社会から逃避すること。社会というノイズから隔絶した自分だけの世界を作ろう——。なんともメルヘンな夢の世界に思われるかもしれないが、しかしその態度は「市場に適合できるかを求められる」現代の空気感に直結する。
「片付け本」がまさに現代で示す「断捨離」が象徴的であるが、ノイズを除去する行為は、労働と相性がいい。自分自身を整理し、分析し、そのうえでコントロールする行為だからである。
コントロールできないものをノイズとして除去し、コントロールできる行動に注力する。それは大きな波にのる——つまり市場に適合しようと思えば、当然の帰結だろう。
このような社会では、市場に出回る商品も極力ノイズを抑えたものになる。その代表例として挙げられるのがいわゆる「自己啓発本」である。読者の「こうなりたい」という欲望に直接的な回答を与えるタイプの本だ。
その時、文学や映画のようなノイズだらけの作品は「情報」として消費されることになる(その最も顕著な例がいわゆる「教養本」である。教養本については僕も昔に色々と書いたのでぜひ読んでほしい)。そこではあらゆる作品が、「目的を達成するためのツール」に成り下がってしまう。たとえば営業の際に相手の気を引くバンドの名前を挙げるために、僕たちは「教養」という「情報」を手に入れようと汗を流すのである。
まあ端的に言って、僕はこんな雰囲気に我慢がならない。あらゆるものがノイズを欠いた「情報」となり、いつでも検索しうるデータの束として認識される社会を、理想の社会として言祝ぐことなど到底できない。いつでも即座に自分が求めるべき情報を手に入れられる社会は、ディストピア以外の何なのだろうか。
インターネットで検索したらどんどん余計な情報が出てきて、いつの間にか何を調べようと思っていたのか忘れていた——そういう偶然が生じる余地を確保しなければならない。
日記を書くことは、偶然を取り戻すための一つの対抗戦略である。生活の中でふと起こる偶然の瞬間を、ノイズとして除去することなく記録すること。何の役にも立たないその一つの記述が、データベースに回収されることなくただそこにあること。
この本を読みながらそんなことを考えた。


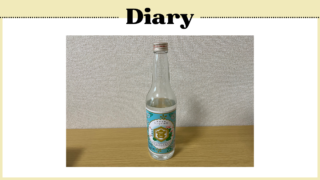
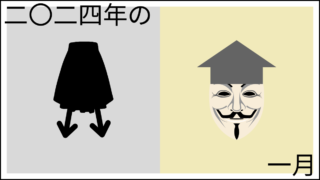


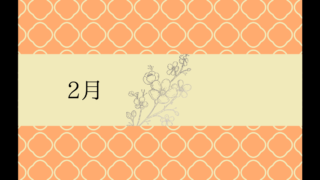

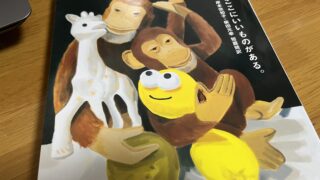
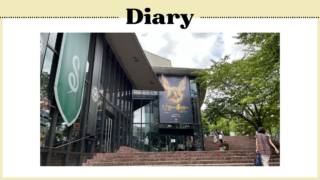
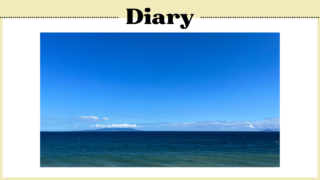
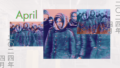
コメント