ユーロスペースで『すべての夜を思いだす』を見る。
監督の清原惟さんは何年も前から名前だけを知っていて、いつか見たいなあと思いながらもその機会がなかなか巡って来ず、ようやく新作が劇場でかかることを聞いてずっと楽しみにしていた。
多摩ニュータウンでの一日が、三人の視点で描かれる。いわゆる群像劇で、筋を要約できない(というより要約する意味を持たない)ような映画だった。特に良かったのは、役者の一つ一つの所作が時間を節約するのためにショットに分割されないところ。
たとえば夏という大学生の女の子が亡くなった友人の実家を訪ねるシーンで、家の前に自転車を停めて、少し逡巡した後で呼び鈴を鳴らす(鳴らしたと思う)場面なんかは、まあ一般的に考えて「自転車を降りる」→「扉の前に立っている」とショットが割られて、その間の数秒を節約するのが定石だと思うのだけれど、この映画ではなんと贅沢にその画面が一つのショットに収められている。
一つの画面はただ一つの機能を持つというのがやっぱり作劇の基本というか、基本的な記号学的処理だと思う。でもその中で失われてしまう、世界に対する身体の反応のあり方みたいなものも確かにあって、この映画ではそういった記号化されえないものが常に画面に充溢しているような感じがあった。
この日は舞台挨拶があって、その中で司会の人や俳優たち、監督自身もこの映画の「音」の良さについて語っていた。その素晴らしさは、それが意味(ないし物語)に還元されることなく、ただそこにあるものとして凛とした存在感を放っていることだと思う。
街を撮るというのは生活を描くということで、生活を描くというのは人生の一部を切り取るということだ。過去を直接示すのではなくて、過去から投射された現在を、つまるところ時間の表皮を描くような徹底がこの映画にはある気がした。でも後半になってビデオの映像が映し出された瞬間に、形象化された、それでも意味を成しえない記憶の濁流が一気になだれ込んでくるような感覚があって、それが無性に寂しく、この一日はもう終わりが近づいていることを悟った。






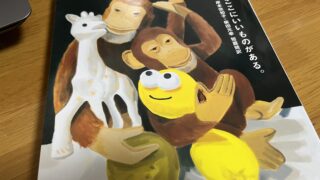
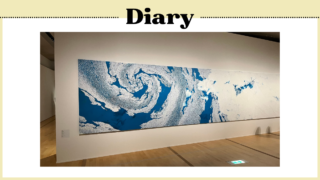
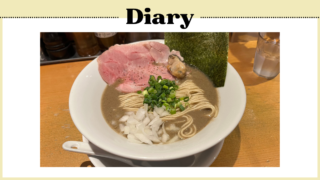
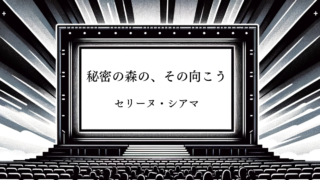



コメント