つい先日の日記で同じ曲しか聞かない月間にすると誓ったのだが、4回くらい連続で聞いているとやはりちょっと別の曲が聴きたくなってしまう。
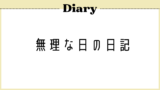
こうした飽きっぽいところが僕の弱点で、そのせいで何につけ能力を身につけることができないことは薄々感じている。だけどこの誓いはそれほど無理をするものではないと思うので、この制限はやめにしようと思う。しかし単にやめただけだと悔しいし、何より
生活を少しずつ変えていかなければならないと思い、今月は同じ曲しか聞かない月間にすることにした。
という目的にも反するから、縛りを緩くすることで折り合いをつけようと考えた。
聞いていたのはミッドナイト・バス。ならばこの一ヶ月はミッドナイトという言葉が入った曲を聞こうと考え、spotifyで検索してみると、最初に出てくるのはTHEE MICHELLE GUN ELEPHANTのミッドナイト・クラクション・ベイビー。
僕はそれほどミッシェルを聞いたりしないので、聞いてみるとかなり新鮮な気持ち。頭の中を涼しい風が通り抜けていく。
ここは無数の社会人が歩く朝の浜松町。スッキリした頭の人間なんてほとんどいないはずだから、今朝の僕は最も頭の冴えたロックンローラーだったに違いない。重い足取りの大人たちを、僕は軽やかに抜き去っていく。
しかしよくよく考えると、ミッシェルを聞いて爽快感を得る、というのは少しばかり世間の感覚と異なる気がする。頭とか振りたくなるというのならわかるのだけど、今朝の感覚としては風呂上がりみたいな感じ。頭の中身がごそっと入れ替わったような。
その理由を考えていると、しばらく経ってその答えらしきものを理解した。
どうやら僕は「ととのって」いたらしい。
サウナと水風呂の往復。巷では大いに流行っている嗜好の一つらしいが、いまいち乗れていない。やってみたことはあるし、確かにこれが合法麻薬だと言われるわけもわかった気がするのだけど、灼熱密室の苦しさを上書きしてくれるほどでもない。
まあ正直なところ僕がそんなふうに感じているのも、サウナとかゴルフとかそういう「いわゆる」っぽい趣味に手を出すのがなんとなく癪だ、という程度の理由にすぎない。単に僕がひねくれいているだけ。サウナに入って「ととのう」みたいなことを言いたくないのだ。ちゃんと流行りのものを受け入れて、型通りの反応をするのが恥ずかしくて仕方がない。くだらない自意識の発露。
まあそれはともかくとして、ラッキーオールドサンとミッシェルの間には確かに限りなく深い溝がある(ここでマリアナ海溝くらい深い、とか書いてしまったら僕の嫌う型通りの反応になってしまう。クリシェは断固として拒絶すべき)。サウナと水風呂ほどの差ではないかもしれないが、サウナの後に33度くらいのお湯に浸かる、くらいの差はあると思う。どっちがどっちかは多分明白なので書かない。
もしも両極端の間で往復運動することがととのうために必要な条件なのだとしたら、僕は意図せずに疲れ果てた脳と身体からねばねばした膿を出していたのかもしれない。「ととのう」ために必ずしもサウナを用いる必要はないのだ。知らんけど。
朝のオフィス街で、真夜中のサウナに入る。
それほど良くもない言葉の響き。まあ別にいいか。
出社したら即カルピスとかをごくごく飲む、みたいな光景を見かけたら、「こいつは仕事前にととのってきたんだな」と認識してくれて構わない。みんなで真夜中に一緒にととのいましょう。
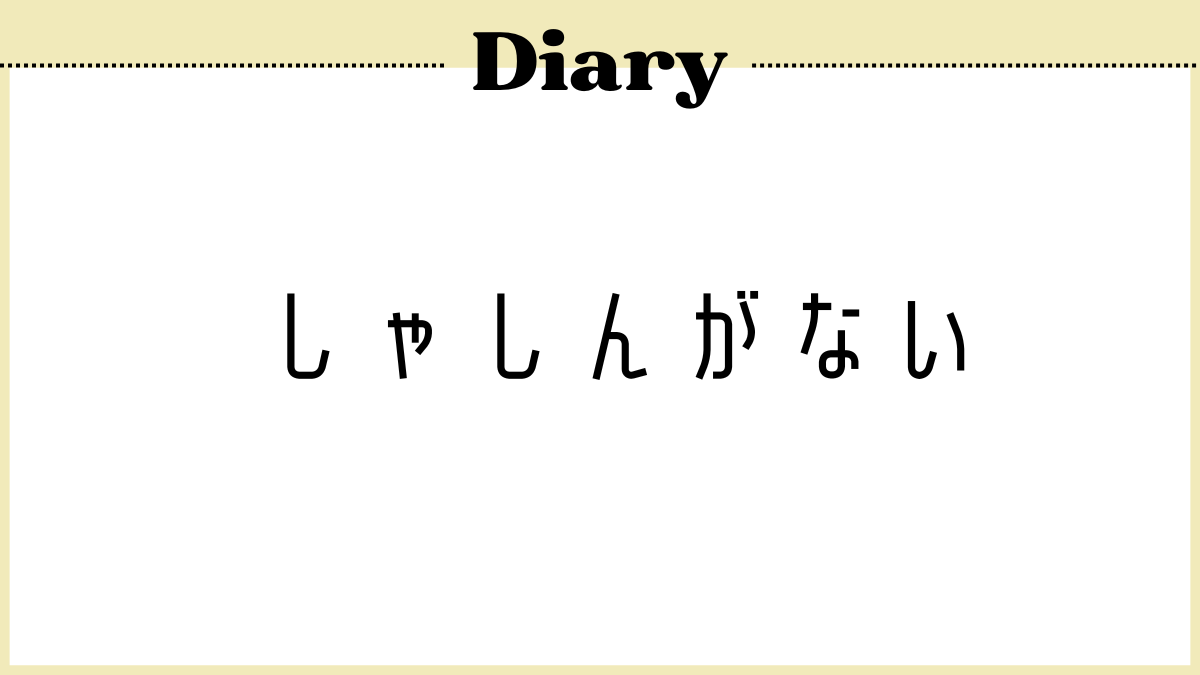

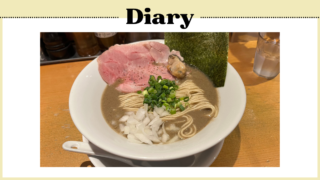
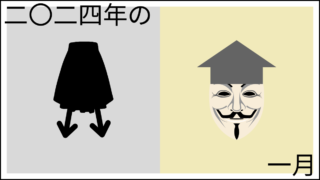






コメント