友人と近くのスーパー銭湯へ。3000円近くするせいか、提供されるすべてのサービスを楽しまなければならないような気がして、忙しなく色々なお湯を点々とする。
いつもはあまりサウナを好まないのだが、そういう理由もあって挑戦。十畳くらいの空間に、大の男が十五人くらいひしめきあっている。サウナだから実際にも暑苦しいのだが、光景そのものもなかなか暑苦しい。
ガリガリの身体をさらに細めながら、「すみません」と小さく呟いて奥の方へ入る。二段になっている座り場の高い方に腰を下ろす。サウナの中にはテレビがあり、半数くらいの人たちはその画面に視線を向けている。残りの半分は、タオルを顔に巻き付けてじっと下を向いている。
すぐに身体が熱くなってくる。とはいえ僕がサウナに入ってから、まだ入り口の扉は開いていない。「もう出たいな」と思うのだが、ここで席を立ったら未来永劫軟弱者との謗りを受けることになるだろう。下を向いて苦悶の表情を押し隠しながら、時間が経過するのをひたすらに待つ。
どれくらいの時間が経っただろうか。僕の右斜め前に座る男性が立ち上がり、小さく伸びをしてサウナを出ていく。それにつられて四、五人が一斉に起立し、そそくさと灼熱地獄を後にする。忍耐力とは、見栄と忖度の連鎖であるとの確信を強くする。
二段になっている列の低い方に座っていた数人が、人の消えた間隙に腰を下ろす。空いたスペースに人がはまり込んでいく姿はまるで逆テトリスだ。流動する人たち。その流れに乗じて、つとめて余裕綽々な顔を作りつつ、僕もサウナを飛び出す。
休日のスーパー銭湯。いかにも休暇と呼ぶべきその時間であろうと、そこには悪しき「男らしさ」や競争原理がぎゅうぎゅうに詰め込まれている。僕はどこで休めば良いのか。そんなことを考えながら、リラックススペースのソファーで背もたれを限界まで押し倒し、「よつばと!」を読む。二巻くらい読んだところで心地良い睡魔が襲ってきて、その生理的欲求に抗うことなく目を閉じた瞬間、これが正しい休暇であることを悟り、なんとしてもこの空間を守らねばならぬと決意する。
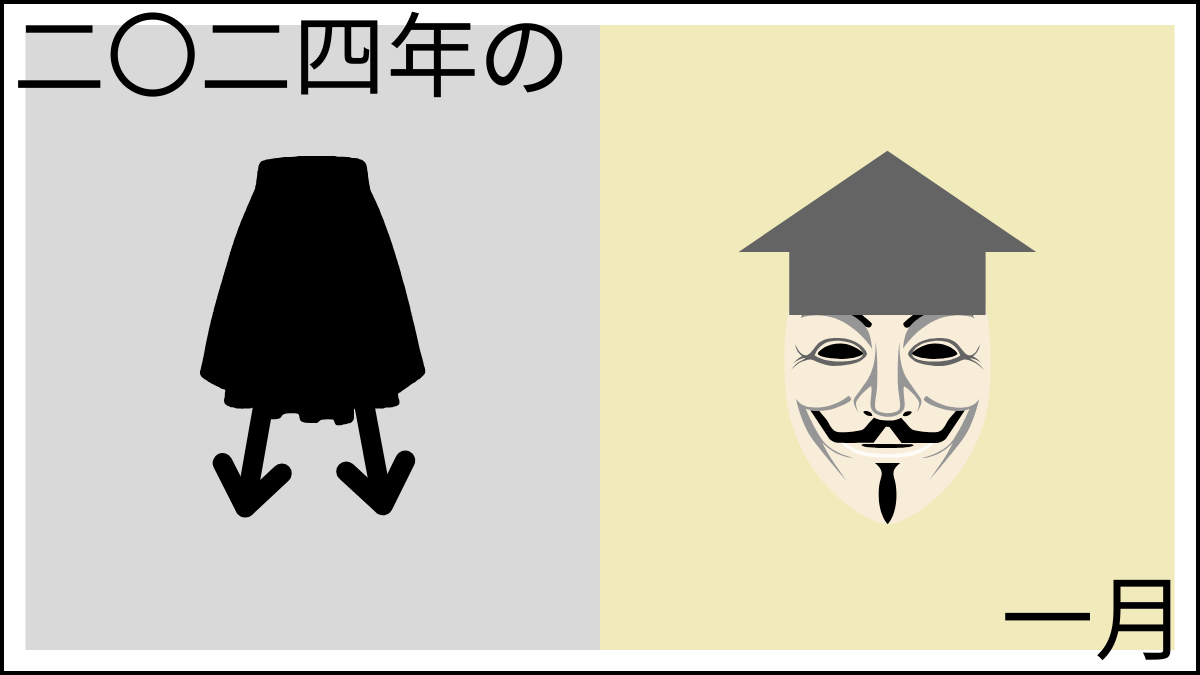

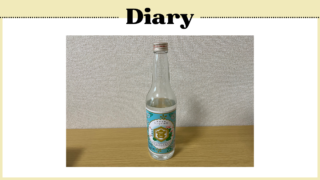
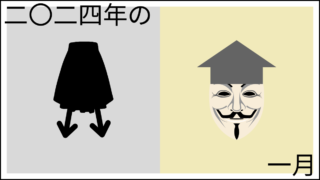


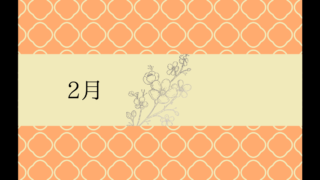
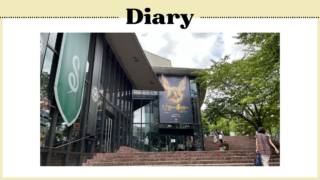
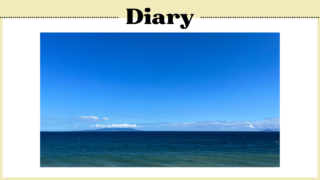
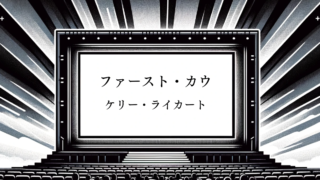

コメント