前置き
五年くらい前、ほとんど小説なんて書いたことのない時期に書いた掌編です。noteにも公開していたけれど、まあ色々と集約したいしということで転記しています。ぜひ。
本文
次の島では全てが透明だった。いや、正確に言うと、生命を宿していないものは全て透明だった。だから僕は遠くから小さな人影が動いているのを見るばかりで、それが島であることに気がつかなかった。ボートは突然何かにぶつかり、その動きを止めた。
崖に勢いよく衝突した船は無残に大破し(それが崖であることを了解したのはずっと後のことだけれど)、僕はひとり冷たい海に放り出された。全身に鳥肌が立ち、心臓の鼓動が早くなるのを感じた。ごつごつした岩を撫でながら上陸できる場所を探し、死に物狂いで足をばたつかせた。前の島でもらったチョコレートを食べ、新調したコートを脱ぎ捨てて僕は大声で助けを呼んだ。体毛の濃い裸の男がその声に気づき、僕に手を差し伸べてくれた。陰部は生き生きとした緑の葉っぱで隠されていた。
男はプツィンと名乗った。
「お前さんは幸運だよ。冬になるとこの島の周りには死体がたくさん浮かぶんだ。まあ、透明だから腐った臭いでわかるだけなんだけどな」
プツィンは透明なタオルで僕の身体を拭いてくれた。いつの間にか僕は全裸になっていた。
「うちに新しいパンツが生えてるから、それを使いな。まあ最初は慣れないかもしれないけどな。あ、隠せよ。この島の警察は島以外の人間も容赦無くとっ捕まえるからな」プツィンは大股で僕の前を歩きながら言った。
「すまんな。散らかってるけど気にしないでくれ」プツィンは大きな葉をもつ木の前で立ち止まると、僕の方に向き直って言った。パントマイムみたいに扉を開ける動きをすると、錆びた鉄が擦れるような音がした。
「もう建て替えないといけないんだ。役所がうるさくてな。透明になっちまった家は猥褻だとよ。老朽化だよ。俺と同じさ。昔はこんなにうるさくなかったんだがな」
僕は家の中でほっと一息つくと(部屋の中はとても暖かかった)、きょろきょろと島の様子を眺めた。どの島にもあるような木製の小屋がいくつか目についた。しかしよく目を凝らすと、そのほとんどが半透明で、奥には人の姿が見える。地面から浮かぶようにして眠っている女性もいれば、生きたイカに頭からかぶりついている少年もいる。頭を噛みちぎられたイカは次第に輪郭を曖昧にしていき、ふと気がつくとそこには美味しそうに口をもぐもぐさせる少年の姿があるばかりだった。
「ずっとこの島で暮らしているんですか?」僕は透明な暖炉の前で体をすくませながらプツィンに尋ねた。火だけがあかあかと燃えていた。
「いや、大人になってからだ。嫁さんがこの島の出身でね。まあでももう四十年になるかな」プツィンは空気椅子に座りながら上を向いて言った。雲ひとつない青空を白い鳥の群れが横切った。
「まあ、あいつも透明になっちまったから、今じゃあこの有様よ」プツィンは寂しそうに黒々と鈍く光る胸毛を撫で、何もない部屋を眺めまわして言った。
「お前さんよ、この島を歩くときは気を付けろよ。どこに何が転がってるかわからんからな」
僕はちょっと散歩をしてくると言ってプツィンの家を出た。扉の場所がわからずあたふたしていると、プツィンはパンツの木と恒星を結ぶ直線上にあると教えてくれた。ドアノブは無い。どうやら鍵という概念はこの島に存在しないらしかった。僕は丁寧に扉を閉め、少し迷った挙句プツィンの目を見て尋ねた。
「この島に、船はありますか?」
プツィンは分厚い扉の向こう側で、僕の言葉など聞こえていないように太い指で耳をほじくっていた。一瞬目が合ったように思えたが、すぐにそっぽを向いて洗濯物を畳みはじめた(ように見えた)。
早くこの島から出て、ナターシャの待つ大陸に辿りつかなければいけない。僕はひどく焦っていた。しかし船はもう使えないし、透明な島には新しい船があるかどうかすらわからない。ともあれ僕は海の上を歩く神になった気分で、島のあちこちを散策した。少なくとも家とか木が生えている間を歩けばあの冷たい海に放り出されることはないだろう。
パンツ一丁で寒い外気にさらされるのは新鮮だった。しかも冷たい風を感じるのは顔だけで、胸のあたりはポカポカして暖かい。プツィンに貸してもらった透明なダウンはなかなか上等なものらしい。これならば裸で雪山を登ることもできるかもしれない。そもそも肉厚で青々とした葉っぱがパンツと呼べるものなのかは定かではないが。
やけに赤い実を収穫している、髪の毛の全くないおばあさんがいた。頭皮が日の光を浴びてつやつやと輝いている。
「すいません、ちょっとお尋ねしたいんですけど」僕は少し緊張しながら彼女に話しかけた。彼女は僕の声を聞くと突然ぶるっと震え、そそくさとどこかへ行ってしまった。その瞬間、束になった髪の毛が僕の頬を優しく撫でた。どうやら彼女の髪の毛はもう透明になってしまったらしい。よく見ると彼女は青々とした下着に比べて輪郭も曖昧で、身体の向こう側が見えるくらいに透き通っていた。
僕はあてもなく島を歩き回ることにした。誰彼かまわず出会った人に話しかけ、この島では船がどこにあるのかを尋ねた。しかし、誰もがさっきのおばあさんと同じように、僕の声を聞くと微かに痙攣して僕のもとから立ち去ってしまう。話すら誰も聞いてくれなかった。
途方に暮れてしまって、小高いところにある(僕は不思議な気持ちで透明な坂を登った)立派な木の下に腰を下ろした。幹は太いが、他の木と比べて葉には生命感がない。茶色く色づいた、ほとんど透き通っている葉が僕の頭上で強い風に吹かれてガサガサと音を立てていた。
僕は透明になってしまった枯れ葉を両手でかき集め、それを枕がわりにして静かな海の上で大の字になった。僕の冒険もこの島で終わりか、と思うとやけに悔しくなって涙がこぼれた。結局ナターシャとは会えずじまいだ。塩辛い涙でぼやけた視界が次第に闇に包まれていき、僕は深い眠りに落ちた。
何か冷たいものが頬に触れ、僕はびっくりして目を覚ました。さっきまで真っ青だった空はどんよりとした灰色に塗り替えられていた。
見間違いかと思って目を擦ったが、それは白い粉雪だった。ナターシャと一緒に遊んだあの雪と同じように真っ白だった。うっすらと雪に覆われた半透明の葉は、まるで息を吹き返したかのように輪郭を際立たせ、僕の上で両手を広げていた。
「意外だろ。雪は生きてるんだ」プツィンが丘の下で背筋を伸ばして立っていた。雪がなだらかな斜面を覆い尽くしている。さっきは気がつかなかったごつごつした大きな岩や、腐りかけている倒木がその輪郭をあらわにしていた。
プツィンの前に雪がこんもりと積もっていて、その真ん中に黄色い花が置かれていた。寒さのためか、その花はみるみるうちにしぼんでいき、輪郭も曖昧に雪の中に溶け込んでいく。僕は顔に積もった雪を払い除けて立ち上がり、プツィンのもとへゆっくりと歩いていった。
遠くからでは気がつかなかったが、プツィンは表情を変えずに泣いていた。涙が鬱蒼とした髭の中に染み込み、首筋を伝って黒々とした胸毛に吸い込まれていった。僕が近づいていることに気づくと、プツィンは透明のコートの中から透明のハンカチを取り出して涙を拭い、少し恥ずかしそうに僕の目を見つめた。
「歳を取るとな、涙もろくなる」プツィンは静かに言った。
「今日はいい天気だったからな、まさか雪が降るなんて思わなかったんだ」
そう言うとプツィンは視線を落とし、小さな雪山をじっと見つめた。
そこには若い女が安らかな寝息を立てていた。きめの細かい白い雪が、彼女の優しげな顔を覆っている。瞳は閉じているが、口元は微かに緩んでいて、どこか僕たちに微笑みかけているようにも見える。僕は思わずあっと声を上げてしまった。
「雪が降る日だけ、俺はこいつに会えるんだ」プツィンはゆっくりとしゃがみこみ、彼女の頬をそっと撫でた。薄い雪がプツィンの温かい手に触れ、冷ややかな空気の中に溶け込んでいった。彼女の頬には透明な穴がぽっかりと浮かんでいる。
「触っちゃいけねえのはわかってるんだ。でもな、こいつの顔を見るとどうも触れたくなる。もしかしたら、今度ばかりは眠たげに目を開けて、なんで起こしたの、って俺に怒ってくれるんじゃないかって」
プツィンはじっと彼女の顔を見つめながら言った。涙が額やら鼻やら口元やらに落ち、彼女の顔は穴だらけになってしまう。
「船は俺が作るよ。どうせこの島じゃ俺しか作れねえんだ。ほんとはよ、お前さんにずっとこの島にいて欲しかったんだぜ。まあいいや、なにせ久々に人と話せたんだ。俺はこの島じゃよそ者だから」
翌朝、僕は透明な船に乗って透明な島を出港した。オールをひとかきすると、その船は姿を現した。黒い体毛が一本落ちている。

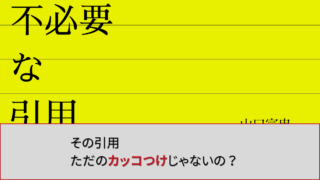
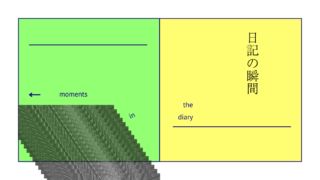

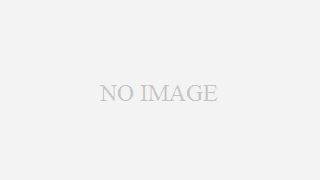
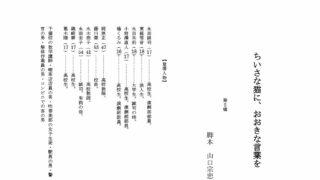



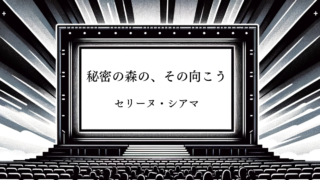


コメント