もう11月が半分過ぎてしまった。対象不明のまま、ただ焦る。
朝から区役所の出張所で、転入届を提出。ここ二日で手続き関係を三、四個は済ませた。偉すぎる。あとは免許の住所を更新し、それを使ってその他サービスの住所変更を行えばとりあえず一区切りがつく。
どうして手続きはこんなにも億劫なのか
この問いについてあれこれ考察したのだが、ちょっと今日の日記では間に合わないし、そもそも大混乱。
というわけで、ChatGPTにこの問題を問いかけ、参考文献を挙げてもらった。読んでいないので、役立つかは知らん。
- Behavioral Public Administration. Oxford Research Encyclopedia of Politics.
- The Political Economy of Administrative Burdens: A Theoretical Framework.
- Why Do Policymakers Support Administrative Burdens? The Roles of Behavioral Science.
- NUDGE, SHOVE, BUDGE, SLUDGE AND ADMINISTRATIVE BURDEN: The Role of Behavioral Scien
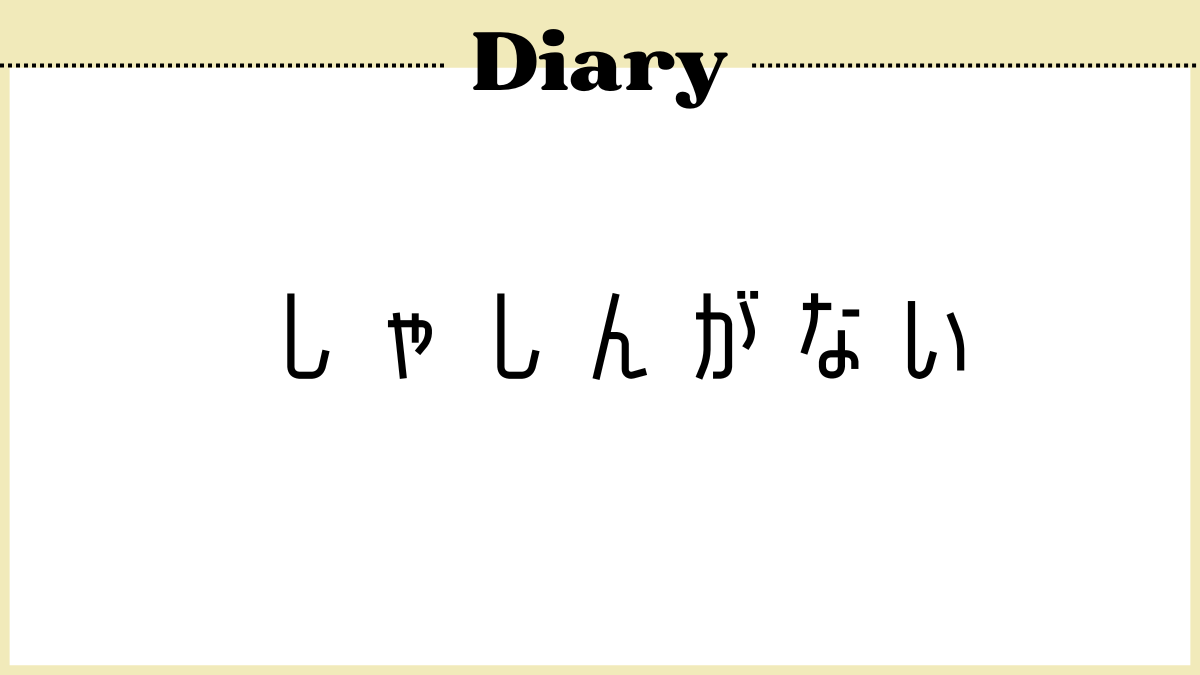





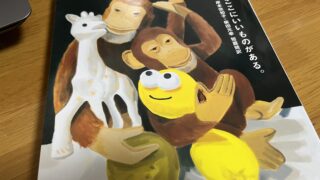
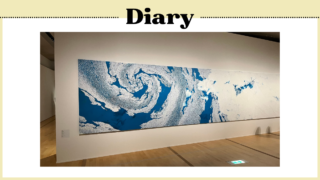
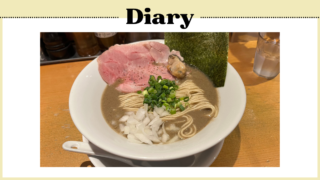
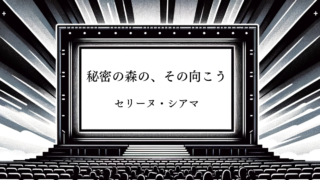


コメント