面倒、というよりも自分の時間を空費するような仕事が発生して心が荒み、職場近くの公園で変なうめき声を発してしまう。むしゃくしゃしたまま電車に乗る。乱れた心で見る世界はとげとげしい。
高校生の頃、苛々を大声に預けて自転車を漕いでいた記憶が蘇る。誰もいないと思っていた公園横の狭い道で、あたりを伺いながら声を張り上げたら、角から自転車に乗ったおばさんが現れ、恥ずかしい思いをした。こういう中途半端さは、いつになってもあまり変わらない。
このまま一日を終えるのは癪だから、あえてちゃんとした生活をしようと気持ちを切り替える。自炊。賞味期限を迎えた豚肉を炒め、前日に切っておいた白菜で蒸し煮にする。白だしと醤油を加え、味を見る。美味しい。ごま油でもあれば良いのだが、今から買いに行くのは億劫だし、別に無いからといって不満では無いのでそのまま食べる。
と、冷蔵庫に二日前作った春菊と豚肉の炒め物があることを思い出す。おかずは作った順に消費していかないといけない。油断すると途方もない時間が経過しており、悲しい粘り気を放つことになる。
というわけで、出来立ての料理をパックに入れ、残り物をフライパンで温め直す。電子レンジがまだ家にないので、いちいち面倒(電子レンジはインフラだよ、と誰かに言われた)。炊いていたご飯にそのおかずを乗せて、夕ご飯が完成。夜十時くらい。
しかしこの丼、あまりにも量が多い。美味しいことは美味しいのだが、単調な味付けのせいもあり、半分くらい食べると飽きがきてしまう。一味をドバドバかけたり、オリーブオイルを垂らしたりして味変をする。
あまりにも満腹の十時半。満たされすぎた僕の身体は、もはや他の動作を必要としていない。本を読んだり、文章を書いたりしたいのだが、意識が散漫になるので、諦めて風呂に入り眠る。
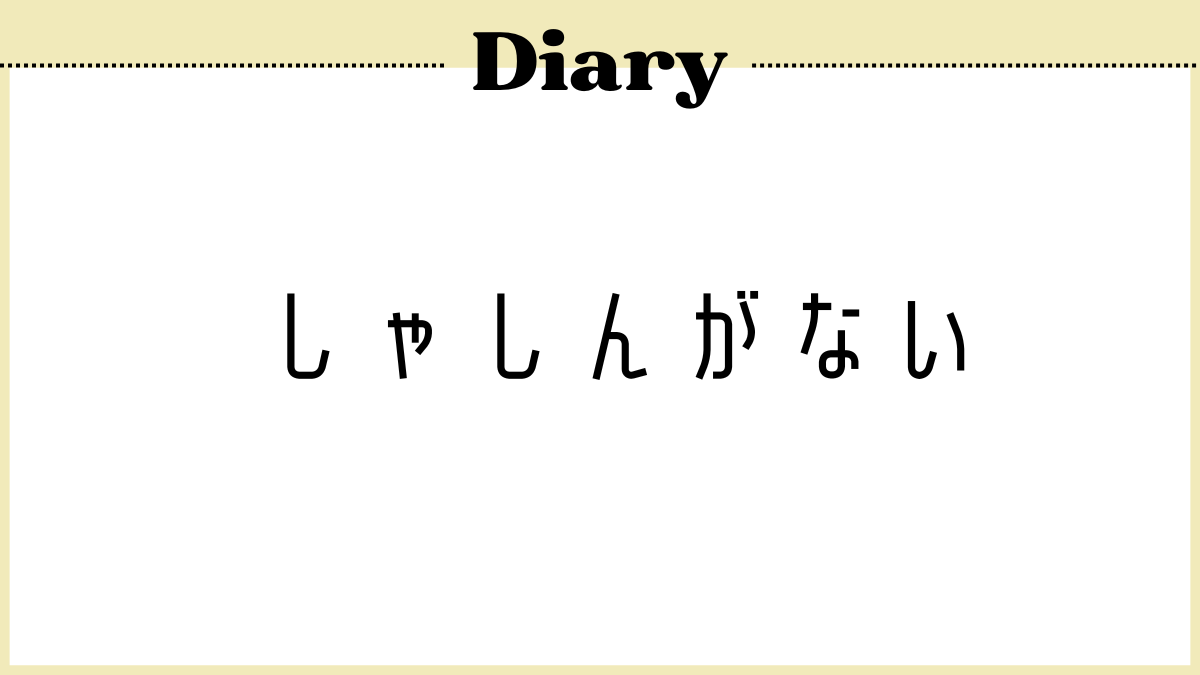





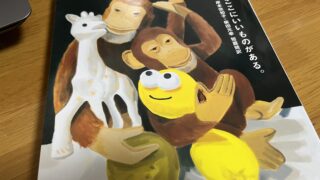
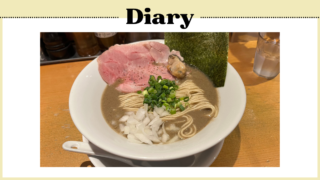

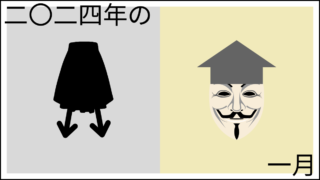


コメント